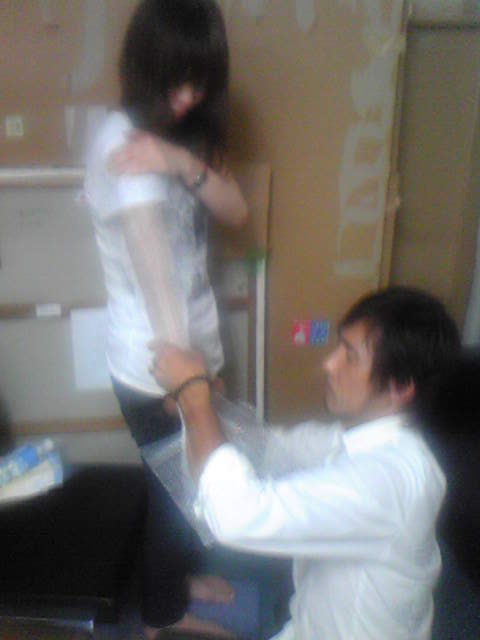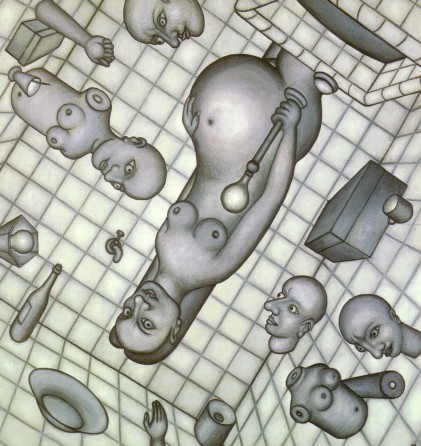August 23,2010
17日~19日まで高松、20日に一旦戻って
21日22日と再度高松
今日から一週間は京都である・・・
瀬戸内国際、結構盛り上がっているようで
是非とも行かなくてはいけないのだが・・・
まぁ上海から帰って、、と言うことになるだろう。
そして釜君の前田寛治大賞展の倉吉展示
もある、、これも上海が終わってから・・・・・
・・・・・・・・・・・・
うーーーん、、、、まぁ、なんとかなるかな??
、、、
この間行き来、交通機関は結構な繁盛で
昨日も帰りの電車は立ちっぱなしであった・・
今週は京都だが、来月の6日~上海渡航
その前に済ましておかなくてはいけない要件
を今週片付ける予定である。
上海との連絡はメールが中心で、CCを含め
ここに来て結構な応酬が繰り広げられている!
実は昨年は出展することだけで精一杯、、
何をどうしていいやらも分からなかった
のだが、今年はこの一年でお会いした様
々な方へささやかな招待状を上海からと
日本から送らせていただいた。
そしてそのメールリストを元に併せて勧誘の
お声をかけさせて頂いている。と言っても、
KFLのF氏K氏の主導のもと上海のLAO
氏を中心に動いていただいているのである。
正直驚いている
思っていた以上に形になっている。
もちろん我々はまだ初めて間がない訳で、、、
国内で行うような訳には当然いかないのだが
しかし凄いと感心した。
なんの根拠もないけど
必ず形になって現れると私は思った。。
もうあと2週間強である。
という今日この頃、、、であるが
遡ること数日前、、
青野女史より相談が入った
昨年釜くんで好成績を収めさせていただいた
画廊で現代美術の括りで企画ができないか?・・と
会期は9月29日から一週間!!
やろう!
と一発で決め
そして概要が決まりました
------------------------
タイトル : コンテンポラリーアートの扉
会期/2010年9月29日(水)~10月5日(火)
最終日は午後4時に閉場いたします
会場/高松天満屋 5階 美術画廊
直通電話087(812)7548
------------------------
基本はCOMBINEの作家で展開するのだが
骨格として京都発という内容を軸に据えた・・
具体的内容に関しては
後日改めてご連絡させていただきます。
が、、、、
百貨店の画廊ではあまりしないだろうな?と
いうようなちょっと面白い展開を企んでます・・・
バタバタの中出来るか否か
こうご期待くださいませ。。。。
21日22日と再度高松
今日から一週間は京都である・・・
瀬戸内国際、結構盛り上がっているようで
是非とも行かなくてはいけないのだが・・・
まぁ上海から帰って、、と言うことになるだろう。
そして釜君の前田寛治大賞展の倉吉展示
もある、、これも上海が終わってから・・・・・
・・・・・・・・・・・・
うーーーん、、、、まぁ、なんとかなるかな??
、、、
この間行き来、交通機関は結構な繁盛で
昨日も帰りの電車は立ちっぱなしであった・・
今週は京都だが、来月の6日~上海渡航
その前に済ましておかなくてはいけない要件
を今週片付ける予定である。
上海との連絡はメールが中心で、CCを含め
ここに来て結構な応酬が繰り広げられている!
実は昨年は出展することだけで精一杯、、
何をどうしていいやらも分からなかった
のだが、今年はこの一年でお会いした様
々な方へささやかな招待状を上海からと
日本から送らせていただいた。
そしてそのメールリストを元に併せて勧誘の
お声をかけさせて頂いている。と言っても、
KFLのF氏K氏の主導のもと上海のLAO
氏を中心に動いていただいているのである。
正直驚いている
思っていた以上に形になっている。
もちろん我々はまだ初めて間がない訳で、、、
国内で行うような訳には当然いかないのだが
しかし凄いと感心した。
なんの根拠もないけど
必ず形になって現れると私は思った。。
もうあと2週間強である。
という今日この頃、、、であるが
遡ること数日前、、
青野女史より相談が入った
昨年釜くんで好成績を収めさせていただいた
画廊で現代美術の括りで企画ができないか?・・と
会期は9月29日から一週間!!
やろう!
と一発で決め
そして概要が決まりました
------------------------
タイトル : コンテンポラリーアートの扉
会期/2010年9月29日(水)~10月5日(火)
最終日は午後4時に閉場いたします
会場/高松天満屋 5階 美術画廊
直通電話087(812)7548
------------------------
基本はCOMBINEの作家で展開するのだが
骨格として京都発という内容を軸に据えた・・
具体的内容に関しては
後日改めてご連絡させていただきます。
が、、、、
百貨店の画廊ではあまりしないだろうな?と
いうようなちょっと面白い展開を企んでます・・・
バタバタの中出来るか否か
こうご期待くださいませ。。。。