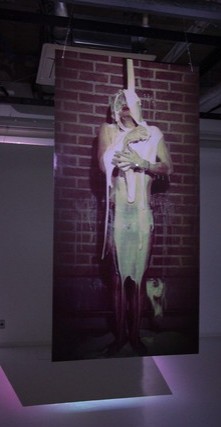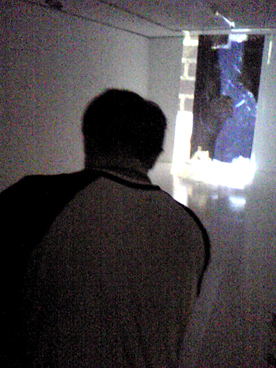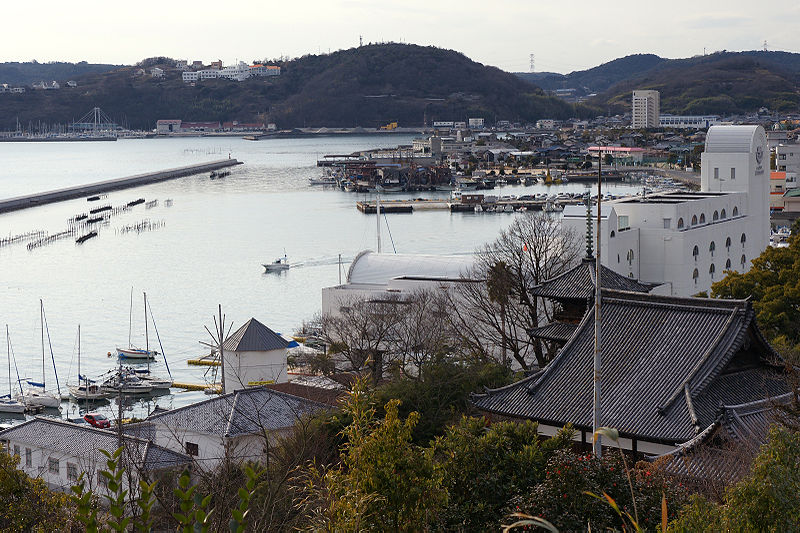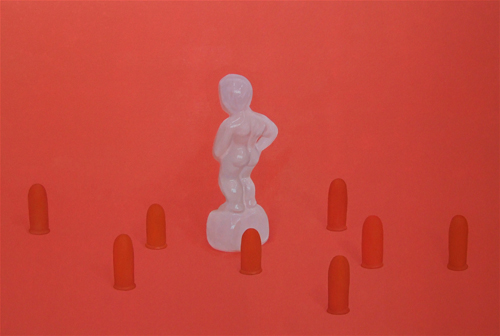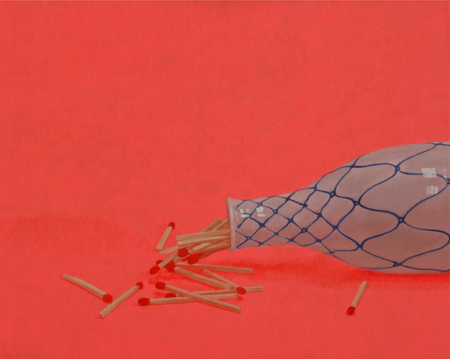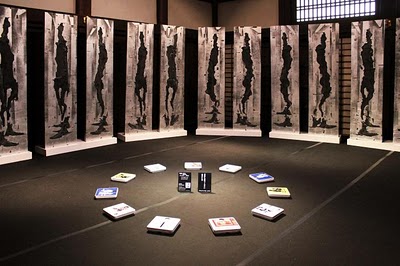下剋上
September 3,2011
この老翁は世の人の成し難き事
を三つ成したる者なり。
将軍を弑し奉り、また己が主君の三好を殺し、
南都の大仏殿を焚きたる者なり・・・・・
下剋上という言葉がある。
最大の下剋上は有史上やはり豊臣秀吉であ
るのは間違いな
いであろう。
しかし、秀吉には出世する途上において、
下剋上という言葉が持つ陰惨なそして卑怯
な雰囲気は感じられない。
主家をひっくり返すのであるから本来は
それ相応の事柄があってなのであろうが、
直接的に主家の滅亡を企てたわけではな
いからそういったイメージとは少し距離
がある。
しかし、実は本能寺の変は様々な原因や
事情が幾層にも重なりあって起きた出来
事あり、秀吉が直接的に絵を描き起こっ
たものではないことは後世の史実の表層
からも認識できるが、信長が殺される地
に赴く遠因を作り出したのが秀吉である
こともまた間違いない史実である。
なぜ?あの信長があそこまで
無防備だったのか?
私はこの部分がかなり前から気になって
いた。
ひょっとすると秀吉はかなりの確率で分
って信長を危険な地域におびき出したの
では?
もしくは本能寺の変の予見をか
なりの精度で持ち得ていたので
は?
これは、その後の劇的な中国大帰しなど
というマンガ並の出来事を敢行できた
最大の要因だったのではないか?という
点を線に結ぶ作業を考えた場合、意外と
スムーズにいくポイントとなる。
よく世間に本能寺の変の情報を得た秀吉軍
の中で、黒田如水が秀吉に天下取りの
大チャンスと耳打ちし、その後かなり警戒
されたなどと言う事がでてくるが、
これはそうではなく、
二人は最初から期待していたことが起こり、
それに粛々と乗じていたったというほうが
実際にはちかいのではないか?と私は考え
ている。
後日この事実を知っている黒田如水に対する
警戒こそが真の秀吉の恐怖する部分だったの
ではないか?と考える方が実は面白い。
黒田如水も日ノ本一の知恵者として、この事実
に対して、あえて口をつぐんでいた方が、常に
秀吉との距離を測るため有効であると判断した
いたのは容易に想像がつく事柄である。
秀吉との距離とは秀吉の天下人としての性格も
あるが、天下を伺うということの距離とも考え
られる。
秀吉が側近に次の天下を望み得る人物は?
と問われ、黒田如水と公言したのは、人の
才能人望の大きさではなく、何かしら腑に
落ちないものがそこには大きな要素として
読み取れないであろうか?
周りの者からしても、えっ?となる回答
であったと思う。家康、利家その他キャ
ラクター的には如水以上のものがひしめ
く中で、なんで?となるのではないだろ
うか。
だからこの回答の最大の本質は瞬間的な
権力奪取の力量だったと思う。
そういう意味では明智光秀的な要素が強く、
まさしく下剋上を果たせるパワーを持ち得
る者が誰かを示したような気がする。
下剋上とは世の中を瞬間に劇的に変える劇薬
であり、その効果は世の中にとって必要悪、
必要不可欠なものでもある。
常識の変革者・革命者である。
これはただ単純なパワーゲームの勝敗とは
かなり次元が違うのである。
冒頭の言葉
この老翁は世の人の成し難き事を三つ成し
たる者なり。
将軍を弑し奉り、また己が主君の三好を殺し、
南都の大仏殿を焚きたる者なり・・・・・
であるが。これは松永久秀の事である。
冷静に判断するとかなりの悪者である。
下剋上という言葉の意味を遥か超越したよ
うな所業であり、世人の常識をかなり破壊
している。
下剋上という言葉の持つ雰囲気を最大に体現し、
後世のイメージにおいてもかさなり合う人物と
言えば私は二人の人物に集約されるのではない
かと判断する。一人は斉藤道三、そしてもう
一人は冒頭の紹介にある松永久秀である。
面白いのはこの二人の人物、信長とかなりの
度合で深い関わりがある。
そしてそれ以上に面白いのはこの二人を信長は
かなり評価し、好意を持っていたという点であ
る。
冒頭の松永久秀に対する言葉は、信長が喋った
内容であり、誰に言った言葉かと言うと徳川家康
に対してであった。
おそらく久秀の毀誉褒貶を紹介する内容ではある
が、そこには、、、、、、
“さすがの俺でも、そこまではせぇへんでぇ!”
みたいな内容と、そんな悪いやつを俺は配下に
しているという自慢・自負みたいなものなど、
この人物に対してかなりの興味と畏敬を持って
いたことがある種伺える内容でもある。。。
斉藤道三は信長の義父であり、戦国時代初期
から中期にかけての栄達者である。
その方法論は世間も知るところであり、信長も
その異形な存在に対しては初期から一目置いて
いたであろう。
が、故にその娘との婚儀においてかなりの大芝居
を演じたのだろう。
しかし、道三は所詮一国を領有したに過ぎないの
であるが、久秀はもっとスケールが大きい。
その視野は常に天下の形勢を大きく動かす位置
にあった。ルイスフロイスなどは本国に天下の
支配者などという内容の報告をしている。
久秀という人物、私は大好きである。
この人物の凄味は冒頭に紹介した所業もさる
ことながら、信長に計2回仕えていることである。
これは逆の意味では2度裏切りを行っていると
いう事である。しかし世間に知られる信長の性格的
イメージから考えても、2度もの裏切りをして許さ
れているいうことだけでもかなり興味深くないだろ
うか?
裏切りとは信頼していたものからすると、最大の
憎悪の対象であり、殺戮の根拠でもある。
しかし、それを許すということは、信長の性格を
考えても、もともと信任厚いからとも言い難いし、、
そのような裏切りをする人物を再々身辺に置くなど
は邪魔くさいと判断してもおかしくないだろう。
それらから見え隠れするのは、常に妙な関係、
信長を中心としたものなのか、久秀を中心とし
たものなのか、よくわからない遠心力が働いて
いたような気がするのである。
信長が天下に進出するまでは天下の支配者として
君臨していたにも関わらず、信長が入京するやい
なやすぐに軍門に下っている。
このあたりの期を見て敏なる感性は並々ならぬも
のを感じるが、この程度は他の大名にも見受けら
れる部分でもある。
これは斉藤道三が最初に信長の器量を見抜いたこ
ととも符号する。しかしこここからである、彼は
信長最大の危機を救う。朝倉義景討伐に参加し、
信長が妹婿・浅井長政の裏切りで撤退を余儀なく
されると、信長と行動を共にし、近江朽木谷の
領主・朽木元綱を説得して味方にし、信長の窮地
を救った。
これは実際に救ったということもさることながら、
撤兵を信長に進言し、具体案を示した点が最大の
功労であったであろうと考える。果たして信長が
簡単に撤兵を決断したであろうか?よくドラマな
どで、小豆袋の両端をひもでくくったものが
御市御両人から届けられ、それに気づき撤兵した
などというシーンがあるが、実際にそんな単純な
ものだったはずはない。
おそらく浅井長政の裏切りが露見した瞬間、軍団
は硬直したはずである。
その状況で献策できるというのはかなりの実績・実力
を有する人物でないといけないし、聞き入れられなけ
れば卑怯者のそしりも免れない。
しかしこの場面でそれが出来たのは久秀しかいなかっ
たように思う。
当然、そこから脱出しなくては自分の身も危ないが、
これまでのこの老人の所業から考えると、早々と
信長を内部から裏切っていてもおかしくはない。
それが出来ないということはかなり緊迫していたか、
信長に対し実直に臣下していたか、いずれにしても
興味深い瞬間である。。
これほどの状況をともにした臣従関係もその後簡単
に久秀は裏切り、謝罪し、許してもらい、また裏切
りという事を重ねる。
そのつど信長が不思議なのは許して来たことである。
明らかにいつか信長を殲滅させよとする腹をもった
人物であり、絶対信用ならない人物でもある。
恐ろしいのは息子を人質に差し出していても平然と
裏切るのである。
それでも信長は常に許してきた。
別の考え方を巡らせば、飼い殺しするということも
考えられる。見せしめとして、しかし、最初の裏切
りについては所領を安堵しているのである。
2回目の裏切りに対しても現実は分らないが、天下
の大名物・古天明平蜘蛛の茶釜を差し出せば助命す
ると言う交渉を持ちかけている。ここまで行くと、
信長の従来のイメージからはかなりかけ離れた人物
に見えてくる。そこまでしてなぜ?この人物を延命
させるのだろうか?
信長には乱世の梟雄に対する憧れがあったとしか思
えない。
今で言う“アイドル”だったんじゃないだろうか?
なぜアイドル足るのか?それは信長自身が戦国時代
の最終の下剋上者たる人物であると想定していたか
らだったのではないだろうか?
松永久秀は信長の軍門に下った瞬間、ある意味歴史的
な役割は終焉した。
しかし、この人物、信長が登場するまでに果たした
役割を考えると、歴史上かなり大きなキャスティン
グボードを握っていたし、冒頭に紹介した古今稀な
悪行を敢行した度量は、それまでの常識的下剋上を
かなり延伸させたパワーの持ち主だった。
このパワーこそが終世の行動規範の中心に常識を覆す
ことを据えていた信長が憧れた部分ではなかったの
ではないだろうか?
信長はあくまで私の所感だが、、、、
最終的には“天皇”を中心とした旧来の国体に挑戦
していたと考えている。
松永久秀の犯した将軍虐殺とは、旧来の体制を無意味
なものにする革新的な常識変革であり、それを主体的
な行動に移したことに対するオマージュを常にもって
いたのではないか?と考えるのである。
明らかに信長は将軍に対して冷酷であり無意味な
存在であることを行動で示し、将軍を自らの天下
とりのツールと利用していた。
この感性はかなり過去から自分の中で明確に構築
されており、その考え方の根幹はやはり、久秀の
将軍虐殺だったと考える。この時代の他の大名に
比べ明らかに最初の段階から遠慮なく将軍を愚弄
しているのはその最たる部分ではないだろうか?
信長が松永久秀に憧れを抱いていたのは別の部分
でも読める。
久秀は、城郭建築の第一人者であり、天守閣の雛形
といわれる「多聞作り」を創始した人物でもある。
それまでの城とはあくまで砦であり、壮麗な権力
の誇示を主たる要素としては兼ね備えていなかった。
しかし、久秀が作った天守閣という概念はただの新
しい建築手法ない。この本質は、自らが具体的に世
の中の絶対君主たる人物であるということを広く知
らしめるのにおいてかなり有効な事であると信長は
気づいたのではないだろうか?
安土城の基本コンセプトは間違いなくこの部分であ
り、聞くと、天皇を迎える部屋まで用意していたら
しい。
天皇に謁見するのではなく、来させるのである。
これは極論かもしれないが、現生の絶対的地位の
確立を具体的造形で示そうと目論んでいたと判断
してもおかしくない。
それらコンセプトのアイデアの源泉はやはり久秀
だったと思う。
冒頭の紹介文、
この老翁は世の人の成し難き事を三つ成したる
者なり。
将軍を弑し奉り、また己が主君の三好を殺し、
南都の大仏殿を焚きたる者なり・・・・・
以外に実はもうひとつそれに匹敵する事柄が
久秀にはある。
武将として初めて城もろとも爆死して果てた
のである!
一説によると天下の大名物・古天明平蜘蛛の
茶釜に火薬をつめ、釜を首からぶらさげ爆死
したとのことらしい。
まぁこれは後世の作り話であり、創作意図と
して、信長が助命の引き換え条件として提示
した天下の大名物・古天明平蜘蛛の茶釜の引
き渡しから象徴的な部分を感じざるを得ない。
しかし、同じ創作意図としても久秀の心情か
ら推察すると、自他共に認める乱世の梟雄と
して悪名を轟かせた自分の最後の演出として
これほど苛烈なものもないのではないだろう
か?
死ねばすべては無くなる!という事を考える
と、神仏を信じず、
「人間五十年 下天のうちをくらぶれば
夢幻の如くなり ひとたび生を享け
滅せぬもののあるべきか」
と敦盛をよく舞った信長の哲学ともピタッと
符号するし、何により
本能寺の変で
”是非もなし”
と言って
爆死した最後は大きく合致しないだろうか??