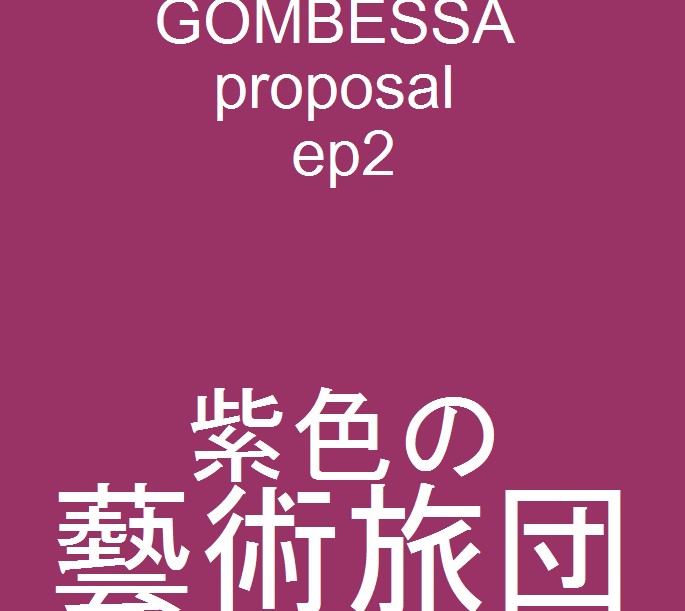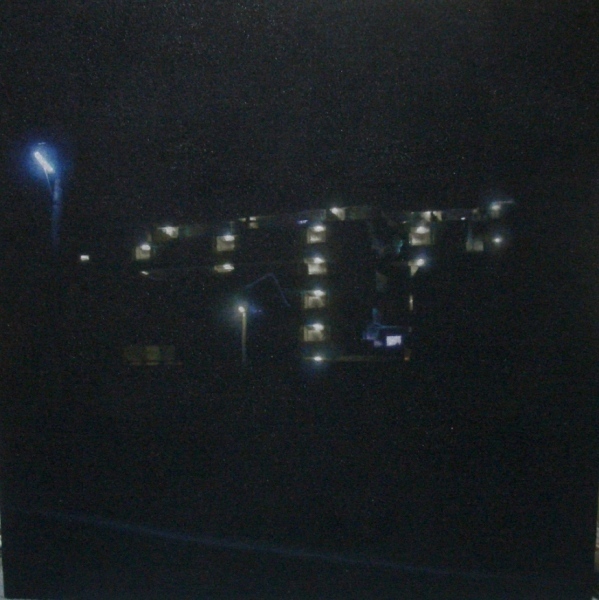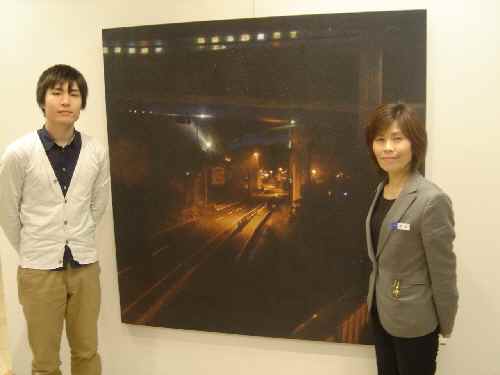December 5,2011
12月は京都と高松にGOMBESSA達が集 結!
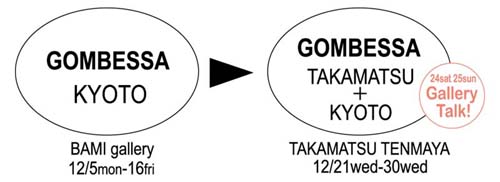
BAMIgallery(kyoto)にて12月5日(月)より開催予定!
GOMBESSA proposal ep2
紫色の芸術旅団

プレスリリース
↓ ↓ ↓
http://www.scribd.com/doc/73241039/
当企画は12月21日(水)より高松天満屋の美術画廊
にて開催予定の「現代美術のカッティングエッジ京都
・瀬戸内のゴンベッサたち」のプレビュー企画として
京都の差kkあを展開いたします。
16日の会期終了後、高松にて瀬戸内地域のゴンベッサ
たちと合流する予定です。
<参 加アーティスト>※写真左より
阿部端樹
武者宏迪
釜匠
松 本央
佐野暁
2011 年 2月5日(月)~12月 16日(金)
BAMIgallery Open
12:00-18:00
【gallery Close】 12/10.11
BAMI gallery
http://combine-art.com/html/gallery/ga_access.php
-------------------
続いて高松天満屋にて12月21日(水)より開催予定!
現代美術のカッティングエッジ
京 都・瀬戸内のゴンベッサたち

プレスリリース
↓ ↓ ↓
http://www.scribd.com/doc/73633432/
京都で編成 を整えたゴンベッサたちが、瀬戸内の
ゴンベッサたちと合流!
本年最後に コンテンポラリーアートの拠点である
瀬戸内地域に集結いたします。
若いアー ティスト達のエッジの効いた能力と
可能性にご期待ください。
<参加アーティスト>※写真左より
阿部端樹 ABE Mizuki
武者宏迪 MUSHA Hiromichi
釜匠 KAMA Takumi
松本央 MATSUMOTO Hisashi
佐野暁 SANO Akira
辻孝文 TSUJI Takafumi
小橋順明 KOBAYASHI Masaaki
炭田紗季 SUMIDA Saki
高松明日香 TAKAMATSU Asuka
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
9 名 の若きアーティストによる ギャラリートーク開催!
12 月24日(土)午後3時~6時
お客様の質疑応答を交え、各アーティスト達の作品に
かける情熱と今後の抱負等を語ってもらいます。
12月25日(日)午後1時~3時
24日と同様、お客様の質疑応答を交え、各アーティスト達
の作品にかける情熱と今後の抱負等を 語ってもらうのと
同時に、地元「塩江美術館」にて同時期開催中の
塩江アートプロ ジェクト
<高松 明日香 イメージの擬 態>
2011 12/17(土)~2012 2/5(日)
についてアー ティスト高松明日 香より展示内容の
説明等紹介さ せてもらいます。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2011 年 2月21日(水)~12月 30日(金)
高松天満屋 5階美術画廊(入場無料)
午 前10時~ 午後7時30分 ※ 最 終日は午後4時閉場
香川県高松市常磐町1-3-1
お問い合わせ TEL087-812-7548
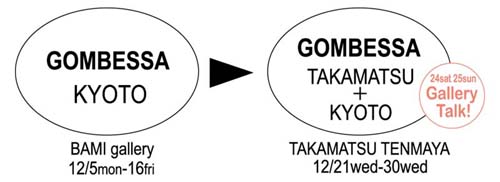
BAMIgallery(kyoto)にて12月5日(月)より開催予定!
GOMBESSA proposal ep2
紫色の芸術旅団

プレスリリース
↓ ↓ ↓
http://www.scribd.com/doc/73241039/
当企画は12月21日(水)より高松天満屋の美術画廊
にて開催予定の「現代美術のカッティングエッジ京都
・瀬戸内のゴンベッサたち」のプレビュー企画として
京都の差kkあを展開いたします。
16日の会期終了後、高松にて瀬戸内地域のゴンベッサ
たちと合流する予定です。
<参 加アーティスト>※写真左より
阿部端樹
武者宏迪
釜匠
松 本央
佐野暁
2011 年 2月5日(月)~12月 16日(金)
BAMIgallery Open
12:00-18:00
【gallery Close】 12/10.11
BAMI gallery
http://combine-art.com/html/gallery/ga_access.php
-------------------
続いて高松天満屋にて12月21日(水)より開催予定!
現代美術のカッティングエッジ
京 都・瀬戸内のゴンベッサたち

プレスリリース
↓ ↓ ↓
http://www.scribd.com/doc/73633432/
京都で編成 を整えたゴンベッサたちが、瀬戸内の
ゴンベッサたちと合流!
本年最後に コンテンポラリーアートの拠点である
瀬戸内地域に集結いたします。
若いアー ティスト達のエッジの効いた能力と
可能性にご期待ください。
<参加アーティスト>※写真左より
阿部端樹 ABE Mizuki
武者宏迪 MUSHA Hiromichi
釜匠 KAMA Takumi
松本央 MATSUMOTO Hisashi
佐野暁 SANO Akira
辻孝文 TSUJI Takafumi
小橋順明 KOBAYASHI Masaaki
炭田紗季 SUMIDA Saki
高松明日香 TAKAMATSU Asuka
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
9 名 の若きアーティストによる ギャラリートーク開催!
12 月24日(土)午後3時~6時
お客様の質疑応答を交え、各アーティスト達の作品に
かける情熱と今後の抱負等を語ってもらいます。
12月25日(日)午後1時~3時
24日と同様、お客様の質疑応答を交え、各アーティスト達
の作品にかける情熱と今後の抱負等を 語ってもらうのと
同時に、地元「塩江美術館」にて同時期開催中の
塩江アートプロ ジェクト
<高松 明日香 イメージの擬 態>
2011 12/17(土)~2012 2/5(日)
についてアー ティスト高松明日 香より展示内容の
説明等紹介さ せてもらいます。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2011 年 2月21日(水)~12月 30日(金)
高松天満屋 5階美術画廊(入場無料)
午 前10時~ 午後7時30分 ※ 最 終日は午後4時閉場
香川県高松市常磐町1-3-1
お問い合わせ TEL087-812-7548