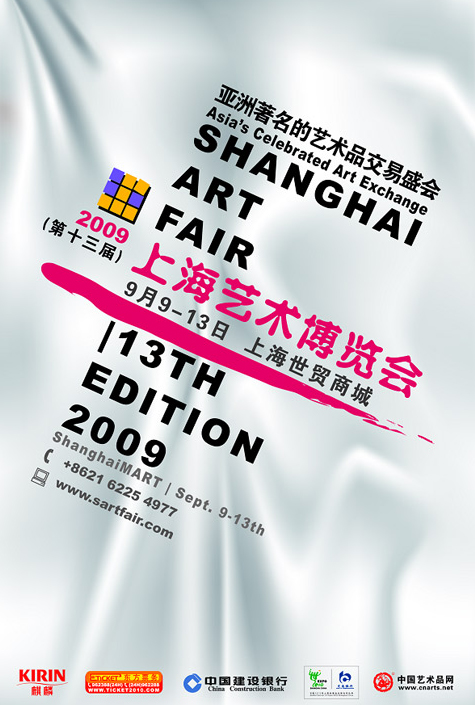光琳へ 14
June 24,2009
紅白梅図の現物を見、細部の確認を済ませ
校正の方向性も確認が取れた。
あとは進めるだけである。
このとき2月初め
10月の発売を想定すれば、残り8ヶ月。
美術館からOKをもらい量産化をスタート
させる時期を考えれば6月。実質的には
残り4ヶ月であった。ギリギリのような
気もするが、とにかくなんとかなる所までやってきた。
ここから大きく分けて3ヶ所の問題点が発生
していた。
まず第一点、印刷。
思いがけずの事であったが、実物を見ると画像などの
印象では感じなかったことであるのだが、白梅の白い
花びらが思った以上に“立っている”のである。
立つとは色が前に出てくる感覚を指すのであるが
強烈に白い花びらが目に飛び込んでくるのである。
初期の想定としては紙そのものの白色でその部分は
構成しようと計画していたが、とてもではないが
その手法では白色が前には出てこない。そうなると
選択できる手段はかなり限られてくる。
シルクスクリーンによる“版”を、このためにだけに
作らなければならない。
僅か数枚の花びらのためだけの“版”…
これは避けられない事情であった。問題は想定コストである。
多少のロスは計算化していたが、このためだけの版を製作
するとなると、原価ベースで?十万円の加算となった。。。
第二点は屏風である。
試作品においてクレームが多少出ていた。もっとグレード
を上げるようにという事であった。根本的な作りを再度
検討する課題であり、こちらも想定原価を大幅に狂わす
要素となって大きく圧し掛かってきた。
この2点の問題点は最終的な小売価格の変更に繋がる
要件であり、再度見積もりを組みなおさなければならなかった。
そして第三点目、これはこの時点では問題化されていなかった
が、現物の劣化した部分、絵が落剥した箇所をどのように補い
認証を得るのか?という問題であった。これに関しては、相手との
コミュニケーション如何ではあるが、取り掛かる前のこの時点で
問題箇所の想定範囲として我々は考えていた。
実際、最大の問題点?か?と想像していた“金箔”部分については
さほど問題ではなく、以前紹介させてもらった、ブロンジ技術に関して
大いに評価してもらっていた。
小売価格の変更に関しては通信販売の企画会社との間で調整を図らなければ
ならない。これは大きな障壁であった。
これまで実は何度か腹の探り合いをしてきたのであるが
どうも、私と彼らには大きなギャップが存在しているなぁと感じてはいた。。
彼らは如何に安く仕上げるか…であり
私は、この企画に見合う価格という考えであり、無闇に安くする必要はない
という考え方であった。暴利を貪るということでない、こういうものの持つ
相対的な価格、、その感覚である。。
しかし、、、、基本的には売れる価格ということである…
安いから売れるわけではない。当然高すぎては売れない。ここが難しいの
であるが、価格感というのだろうか、やはり商品が持つ、持たされる雰囲気
や性格によってその値段はかなりの幅を持つこととなる。
美術品の場合、基本は“インフレ商材”でなくてはならない。需給のバランス
で需要が勝つバランスを如何に組み立てるかこれが重要な要素となる。
しかしながら、だからと言ってインフレーションがハイパーにまでなると
価格感が失われることはもちろんだが、特定の人間しか買うことが出来なくなる。
今回の場合、基本は通信販売であり不特定多数とまで広範なターゲットではない
にしてもある程度のインフレ要素を含みながらの“数”を想定しての計画であり、
その数が計画通りの答えを出せるジャストな金額が幾らなのか?という事であった。。。
正直、最初の検討段階で通販側から提示された“指値”は、私の感覚では
安すぎるものであった。これは原価からの積算によって無理という筋の問題
として捉えていたわけではなく、先に述べた“価格感”からしてオカシイと
感じた事であった。良いモノが安くという状態は平均的な商売の想定では
パフォーマンスが良いと思う。しかし美術品というものの性格は決して
そうではない。言葉は悪いが通念として“安物”という感覚にしかならない
場合が多にしてある。“物”にしてしまうと価格は取れない。。。。
付加価値というものが存在する。これは無闇やたらに乗せていいものではない。
しかし乗せなくてはならないものも存在するのと同時に乗せる資格というものが
ある。
私は今回の企画は、この資格が充分あり、また、その為の営為努力を最大限に
必要とするものであると考えていたのであった。
通販側も美術品を今回始めて扱った訳ではない。
価格感も充分持ち合わせてはいる。
しかし、最大の問題は自社内での過去データーの比較でしかなく、世間全般
の美術市場や感覚をマーケッティングした相対的な価格感ではないのである。
だから、オカシイのであるが、ターゲットが国宝と言えど、“前例主義”の
中から全てを想定してしまうのであった。
この点については数回話し合ったが、なかなか折り合いがつくことなく、そのまま
になっていた。当然その価格近辺という事で私は制作に取り掛かっていたが、結局
最終的な小売価格に関しては、この時点ではなにも決まってはいなかった。。。
丁度良い機会だ!と思った。
再見積もりを詳細に組みなおすと、やはり先方が想定していた小売価格の50%UP
程度になる。この価格感は正直悪くは無かった。
コストが上がる事情も踏まえて、この問題を決着しようと先方へ伺った。
もろもろの説明をし、こちらの考えも述べた。
そこで結論として価格を明示したのであるが、黙って聞いていた担当の顔が見る見る
変わるのが分かった。。
もう今なにを言われたのかは覚えていないが、かなりエキサイトしていた。。
私も先方も・・
しかし私の答えは一つであった。
これ以上は安くならない。
安くするつもりもない!
事実安くは出来ない事情もある、そしてなにより私としては先方の
考える値段はどう考えても納得できるものではなかった。。
強気に出れる条件が私にはあった。
これで駄目ならこの会社とこの仕事はもう進めない!
自分たちでできるものならやってみろ!
という生意気な感情が口元まで出かかっていた。。
相手もそれは充分理解していたと思う。
別れ際に、この価格では再度検討しないといけない。
会社の会議にかけて結論を出します…
場合によっては…
という事であった。。。
当然相手の事情もわかる。仕入れ予算や広告宣伝費等の経費を既にラフながら
組み、その計画をもとに会社の了承を取り付けて進めているわけであるから、それが
全てとは言わないまでも、商品の仕入れ価格が50%も上がるとなると、それは
高すぎるという結論に変更しかねない。という事は計画中止となる可能性が濃くなる
。。。。。。
私としても正直、突如中止となれば困るのは事実であった。
ここまで様々な関係者を動かし、それぞれに実際発生している金銭もあった。
しかし中止となってもこの屏風の製作は続行しようと決意していた。
そして独自に売る方法を考えていこうと勝手に考えていた。それは逆に自信が
あったからだ…
この物件をそうそう何処もが出来るはずは無い!
必ずそう簡単に放棄はしないだろう!と同時に、仮に中止となっても
この物件は必ず活かせる道がある。。と確信していた。
後は先方がどう考えるか次第であった。
が、、、、やはり納得がいかないので
戻り次第、20枚に渡るレポートを書いた。
そこにはこれまでの進捗状況についてや、この仕事における特殊事情
その他、諸々の難題等を時系列にして詳細に説明させてもらった。。
これまで何度も経過報告はしてきたから知った事情ではあるが、再度
書く事にしたのは、この商材は“特別”であるという事を伝えたかった
のである。
国宝!
国民の宝をモチーフにしている!
これは一企業の過去のデーターで捉える対象ではなく、もっと
広義な意味においての価格感を考えるべきで、過去の事例、自社の商材
と並列して考察するべきものではないという私なりの信念であった。
このレポートがどのように受け取られたのかは知らない。
憎憎しげな感情を掻き立てたやもしれない…いや確実に
そうであったであろう…
しかし喧嘩しようが、中止になろうが、私はそれで良かったと
自分なりに結論付けた。
営業的にはあまり良いことではないが、もうこの頃の私にとって
この屏風は、ただの“物”として冷静にシビア-に捉えられるもので
はなかった。本来これでは駄目であることは分かっていた。。
もっと冷徹に利益を直視しなくてはならない、、、
でも、、、それだけではこの屏風は出来ないだろうナァ・・と、、、、
なんとなくではあるが、、そういう想いがあったのも事実であった。。。。
単純な物作りで終わってはいけない、そこに絶対的な情熱、思い入れ、
畏敬…そんなものが大きな割合を成さなければ…
仮にそれらしいものが出来たとしても
絶対に感動は生れない。
それは“売れない”という事でもある。
先方に下駄を預けたような形になったが、
私としては“光琳”に下駄を預けた気持ちであった!
暫くして回答がきた
“続行”
という結論であった。。。
つづく。。
光琳へ 13
June 18,2009
さて、2か月が過ぎ
いよいよ美術館に伺う日がやってきた。
この年は例年と違い、紅白梅図は2月からの公開
ではなく、一月の確か28、29あたりから公開していた。
美術館側に校正の方向性の確認が、この日の重要な仕事であった
のであるが、それと並行して実物の確認、これも重要な仕事であった。
これから具体的に作るにあたり何度も確認できるものではない。
しかもこの伺った日あたりから僅か約40日間の展示。。。
今回見るというのは、この一回で実像を網膜に焼きつけなくては
ならないということであり、それぞれ持ち場ごとに大事な箇所
当然印刷を受け持つ者は細部にわたる色の確認、屏風制作を受け持つ
ものは細部の作り、我々はやはり全体の印象・・・と、、それぞれ
が明確な意識をもって臨んだ。。
この日、伺ったメンバーは、私、私の部下の鳥居、印刷会社からは
営業のNさん他技術者3名、屏風制作会社営業のFくん、美術館への
担当窓口商社の営業Kさん、以上総勢8名であった。。
予定の時間までロビーで雑談をしながら副館長、学芸課長を待った。
30分ほどして事務所に来るようにと取次の女性から言われ、皆一列
に並んで事務所に入っていった。あらかじめ訪問メンバーは伝えていたので
あるが、やはり実際、大の男がゾロゾロと8名、そう大きくない事務所に
入っていくと、なんとも言えない圧迫感がうまれ、美術館の方も一瞬
ひるんだように思えた・・・
早速に東文研のデーターを広げ確認に入る。
美術館側は、驚くこともなく、あっさりと、欠損、破損部分等は
商品として美しく仕上げてください・・という事であった。
一般のお客様がお持ちの美しいイメージを再現してください。
と、言う方向性の指示であった。。。
正直、、私は少し残念であった。
実は、どこまでも忠実に現在を再現するということに、少し
欲求をもっていた。実際その方が“面白い”し付加価値を考えても
いいのではないか?と誰にも特に言わなかったが、そんなことを
考えていた。
実際、、、今でも残念なのである・・・
さて、
今回の問題は、このような答えを得て解決というほど生易しいもの
ではない。現状以外の“美しい紅白梅図”となると、一体どの時点での
経年劣化を再現すれば良いのかという問題が生まれるのである。
傷んでいるものであるのは間違いない、その傷み具合をどの程度にするか?
これは制作側の想像、イメージの世界に託されることになるのであるり、それを
美術館側のイメージとどうチューニングするか?実に難しい作業となる。。
まったく新しい、、それこそ光琳が書上げた当時を想像で再現したとしても
美術館の学術的見解に沿うのかどうかという問題が生まれる。しかし
この場合意外とリセットしてやり直しやすい部分があるが、今回のような
経年劣化のどの時点が“美術館の言う美しさ”になるのか・・・・・・と
言うようなものの場合、、、、改めて校正回数は多い!と腹をくくったので
あった・・・・
一通りの確認が終わろうかという時に、学芸課長から
「では、今の確認事項を踏まえて、紅白梅図を見にいきましょう!
まだ閉館時間ではないですが、今年は例外的なスケジュールで一月から
公開してまして、実は案外ご存じない方が多く、今は閑散としてます、
ちょうど良い機会に来られた。」
と声をかけていただき、課長のあとについて8名がゾロゾロ紅白梅図
の展示場へ向かった。
薄暗い展示場の一番奥
ぼぉ----と浮かび上がる
紅白梅図・・・
国宝。
美しい・・・
中学時分に教科書で見た、あの紅梅の根元、、人の足のような
間違いなく本物だ・・・・
しかも、、
頭の中に入っていたサイズより、、数段大きく感じる。。。
風格と威厳。
これほどまでに・・・・・“ 凛 ”としている絵画は
そうは、ない!
ある意味驚愕であった。
写真、書籍、ポスター
まったく別物だ。
これを1/2で複製するのか・・我々は。。
と、、しばらく8名は展示ガラスの前で立ち尽くしていた。。。
ぼぉ----と見ていたのであるが、気づくと
印刷会社の4名はカラーサンプルを取り出し屏風正面に陣取り
ああでもないこうでもないと打ち合わせを始めた・・・
立ったり座ったり、寝転んで下から眺めたり
顔をガラスにくっつけ・・・・・
学芸課長から
まだ完全な閉館ではないですから・・お客様のご迷惑にならな
いように!
と、注意されるぐらいのハイテンションで4名がガヤガヤと大声
でやりだした。最初は其のつど注意していた学芸課長も半ば呆れ
たように、、、諦めて見守ってくれた・・・
まるで子供がおもちゃ屋のウィンドウの前で、騒ぎはしゃぎ見ている
風景であった・・
閉館を約30分超えても我々はその場を離れようとはしなかった。
気づくと展示場に入ってからゆうに一時間は過ぎていた。。。。。。。
私も同じく、じっと何度も様々な箇所を見つめ続けていた。
あることに気づく・・・
あきない・・・
この絵は相当な時間見続けてもあきない。。。
そして、一番大事なのは、この威風堂々とした佇まい。。
これを果たしてどれほど・・・
と、ぼ------と考えていると、、、学芸課長から
「本当は絶対にダメなんですが、皆さんの熱意、これに
少し応えさせてもらいます。。」
「??」
「お一人“5秒”以内」
「??」
「この隅からガラスケースを開けますので、ガラス越しではない
実物の色を見て下さい。何度も言いますが一人5秒です。それ以上は
コンディションが変わりますので・・・」
皆、、、“えっ”とお互いの顔を見合わせた!
慌てて、それぞれ、ハンケチを口に当て、学芸課長が立つ
ガラス開口部に一列になって並んだ・・
それでは、と順番に5秒づつ学芸課長がガラスを開け閉め
という作業を開始した。。
この場合、技術者からの順である。
当然私や私の部下は一番最後。
なんとも言えない嬉しい待ち遠しい気持ち・・・・
が、、、、、技術者の執念!
学芸課長が“ちょ、、ちょっとぉ!もうその位に!”と言う位
食らいつき時間を引き延ばし見つめたのである・・・
そしてイヨイヨ私、、であったが、、、最初からの技術者の引き延ばし
にイライラしていたのか、、私は本当に5秒以内、、3秒くらいであった。。
。。。。。。。。。。
でも、、わずか開いたガラスから覗き見た
紅白梅図は
とんでもなく
大きく見えた。。。
つづく。。