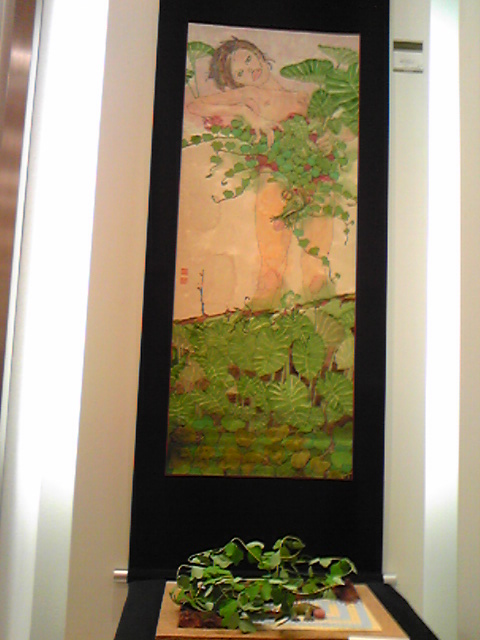始まりました!Green Salamander in takamatsu
November 6,2009



田村さんとの出会い 7
November 2,2009
November 2,2009
田村さんが会社を辞められたことから
他のデザイナーと仕事する機会が徐々に
増えてきていた。
しかし、正直、田村さんほどしっくりくるものは無かった。
確かにデザイナーにも得手不得手というものがあるだろうし、
私自身が感じる仕事のパートナーとしての相性もあった。
だから、たまに田村さんにはチョコチョコ相談を兼ねた
仕事の依頼をしていた・・
それから2,3年、景気もどんどん悪くなり、改装などという
経費のかかることもめっきり減り、デザイナーと仕事をするな
どということがほとんどなくなったころ、何気なく田村さんに
連絡した。
どうしてはるかんなぁ?
ほんのそんな気持ちからで、まったく用件はなかった・・
電話口の田村さんの声はすこぶる元気で溌剌と・・・
こういう言い方をすると問題ではあるが、、会社勤めされて
いるときより活き活きされていた・・
近況を聞くと
工房を借りて、今そこで木工やら、陶芸やら、そんな事をして
楽しんでいるということだった。
いつかお邪魔します、というような事をいってその時は
電話を切った。
それからもチョクチョク電話はしていた。
その都度、今何していますか?と聞くのだが・・・
ある時から、「いやぁ、木で石を作ってて・・・」
と言うような事を語り出された。。
木で石??なんのこっちゃ?
よく分からなかったが、田村さんがやることだから、、、
なんか面白そうな雰囲気は感じていた。。
それから一年後
突然、田村さんから手紙が届いた。。
封をきり、手紙を読むと
「第25回朝日現代クラフト」優秀賞受賞を受賞しました、、、、云々。。。
えぇ-----------------------?
突然、、、、、なに?どういうこと??
慌てて電話を入れた。
少し疎遠になっていた一年位の間に、コツコツと作品製作し
おもいきって出品したら、優秀賞をもらったということだったのだ・・・
はぁ~。。。。一体なにをするやら。。。。それにしてもやっぱりすごいナァ!!
しばらくして新聞で作品の写真を見、その後実物も拝見した。
これは!
と、、、間違いなく私の“琴線”を大きく弾く衝撃があった・・
工芸や木工、、そんな手仕事の範疇ではない。地味ではあるが
迫力ある芸術表現で、しかも沸き立つような作品が持つ独特の
“長い生命感を伝えるような時間軸”が察知できた・・
あたかも古よりあったような・・
当然、作為的にカタチを作り出さなければ作品としての
存在は浮かび上がらない、しかし、その作為的なものと無作為の
境界の皮膜の中に存在するような、少し言葉は悪いが粗野さと
気づかないところで漆やその他の磨きなどで手を加えた繊細な
仕事が、人間の固定観念と常識の狭間に存在する妙な不可視
感を田村さん独特の解釈により自然界の実存として作り上げ
ていた・・
それから一年後、新たな工房を開設したと聞いた。
そこは京都南部の宇治田原という山奥で、宇治茶発祥の地
であった。
いつか行かねばナァ!と思いつつ月日が過ぎていき、様々な
紆余曲折があったが、諸々を具体化すべく、COMBINEを構想
するような事になった。。
この時、アーティストの選定を、それまで付き合い
のあった方、新たに付き合う方を含めて約半年位の
時間をかけて選び出していたのであるが、実は真っ先に
頭に浮かんだのが田村さんだった。。。
これには明確な理由があった。
間違いなく作品とその内容が私の琴線を弾いていたことも
あったが、実は年齢もその大きな要素ではあった。
正直、私は若者だけで固めるということに抵抗があった。
出来れば各年代の男女アーティストをランナップしたかったのだ。
今の時代を表現する作家たち、これは基本的なコンセプトなのだが
今を描くのが若者だけというのには少々の疑問があった。20代
30代、40代、50代、60代・・・それぞれが過ごした時間が
あり、その立ち位置から見た今というのが面白いんじゃないかなぁ?
と感じていたのと、どこか陣容がタイトに尖ったものも、その個性を
鮮明にするには効果的なのかもしれないが、多様さが足りないのでは?
とも感じていた。
私は今もそうなのだが、説明の便宜上として現代美術という言葉は
使うが、自分が取り扱っているのは、あくまで芸術表現だということ
であり、そのコンセプトが示し具現化する意味においては、やはり
この時代に生きている様々な人の多様な考え方をいかに自分が
考えるものと合致させ、如何に面白く提示し、喜んでもらい
関心し感心してもらえるか?ということだと考えている。
そういう意味で、是非、田村さんには参加して欲しかったし、
なにより・・・
ドン!とした、
支柱になってもらいたかったのである。。。。
COMBINEを立ち上げて程なく
新しい工房に伺い参加要請させてもらった。
快く快諾してもらい、、、その流れで約一年後の個展を
了承してもらった。。。
最初から一年経った時には田村さんの個展!と決めていた。
おそらく、、右へ左へとフラフラするであろう一年後
気持ちもひょっとしたら折れかけているかもしれない
一年後。ほとんど可能性は低いが、ちょこっと成功して
るかもしれない一年後・・・・
様々なことがほんの少しだけ見える一年後・・・
そのタイミングで、田村さんには“ドン”と登場してもらいたかった
のである。。。。
その個展が、いよいよ一ヵ月後にせまってきた。。。
最初の出会いから8年
まさか、方やギャラリーのプログラムディレクター
方やアーティストとして再会するなどとは・・・・
こんなワクワクする
邂逅は、、、
初めてかもしれない。。。
他のデザイナーと仕事する機会が徐々に
増えてきていた。
しかし、正直、田村さんほどしっくりくるものは無かった。
確かにデザイナーにも得手不得手というものがあるだろうし、
私自身が感じる仕事のパートナーとしての相性もあった。
だから、たまに田村さんにはチョコチョコ相談を兼ねた
仕事の依頼をしていた・・
それから2,3年、景気もどんどん悪くなり、改装などという
経費のかかることもめっきり減り、デザイナーと仕事をするな
どということがほとんどなくなったころ、何気なく田村さんに
連絡した。
どうしてはるかんなぁ?
ほんのそんな気持ちからで、まったく用件はなかった・・
電話口の田村さんの声はすこぶる元気で溌剌と・・・
こういう言い方をすると問題ではあるが、、会社勤めされて
いるときより活き活きされていた・・
近況を聞くと
工房を借りて、今そこで木工やら、陶芸やら、そんな事をして
楽しんでいるということだった。
いつかお邪魔します、というような事をいってその時は
電話を切った。
それからもチョクチョク電話はしていた。
その都度、今何していますか?と聞くのだが・・・
ある時から、「いやぁ、木で石を作ってて・・・」
と言うような事を語り出された。。
木で石??なんのこっちゃ?
よく分からなかったが、田村さんがやることだから、、、
なんか面白そうな雰囲気は感じていた。。
それから一年後
突然、田村さんから手紙が届いた。。
封をきり、手紙を読むと
「第25回朝日現代クラフト」優秀賞受賞を受賞しました、、、、云々。。。
えぇ-----------------------?
突然、、、、、なに?どういうこと??
慌てて電話を入れた。
少し疎遠になっていた一年位の間に、コツコツと作品製作し
おもいきって出品したら、優秀賞をもらったということだったのだ・・・
はぁ~。。。。一体なにをするやら。。。。それにしてもやっぱりすごいナァ!!
しばらくして新聞で作品の写真を見、その後実物も拝見した。
これは!
と、、、間違いなく私の“琴線”を大きく弾く衝撃があった・・
工芸や木工、、そんな手仕事の範疇ではない。地味ではあるが
迫力ある芸術表現で、しかも沸き立つような作品が持つ独特の
“長い生命感を伝えるような時間軸”が察知できた・・
あたかも古よりあったような・・
当然、作為的にカタチを作り出さなければ作品としての
存在は浮かび上がらない、しかし、その作為的なものと無作為の
境界の皮膜の中に存在するような、少し言葉は悪いが粗野さと
気づかないところで漆やその他の磨きなどで手を加えた繊細な
仕事が、人間の固定観念と常識の狭間に存在する妙な不可視
感を田村さん独特の解釈により自然界の実存として作り上げ
ていた・・
それから一年後、新たな工房を開設したと聞いた。
そこは京都南部の宇治田原という山奥で、宇治茶発祥の地
であった。
いつか行かねばナァ!と思いつつ月日が過ぎていき、様々な
紆余曲折があったが、諸々を具体化すべく、COMBINEを構想
するような事になった。。
この時、アーティストの選定を、それまで付き合い
のあった方、新たに付き合う方を含めて約半年位の
時間をかけて選び出していたのであるが、実は真っ先に
頭に浮かんだのが田村さんだった。。。
これには明確な理由があった。
間違いなく作品とその内容が私の琴線を弾いていたことも
あったが、実は年齢もその大きな要素ではあった。
正直、私は若者だけで固めるということに抵抗があった。
出来れば各年代の男女アーティストをランナップしたかったのだ。
今の時代を表現する作家たち、これは基本的なコンセプトなのだが
今を描くのが若者だけというのには少々の疑問があった。20代
30代、40代、50代、60代・・・それぞれが過ごした時間が
あり、その立ち位置から見た今というのが面白いんじゃないかなぁ?
と感じていたのと、どこか陣容がタイトに尖ったものも、その個性を
鮮明にするには効果的なのかもしれないが、多様さが足りないのでは?
とも感じていた。
私は今もそうなのだが、説明の便宜上として現代美術という言葉は
使うが、自分が取り扱っているのは、あくまで芸術表現だということ
であり、そのコンセプトが示し具現化する意味においては、やはり
この時代に生きている様々な人の多様な考え方をいかに自分が
考えるものと合致させ、如何に面白く提示し、喜んでもらい
関心し感心してもらえるか?ということだと考えている。
そういう意味で、是非、田村さんには参加して欲しかったし、
なにより・・・
ドン!とした、
支柱になってもらいたかったのである。。。。
COMBINEを立ち上げて程なく
新しい工房に伺い参加要請させてもらった。
快く快諾してもらい、、、その流れで約一年後の個展を
了承してもらった。。。
最初から一年経った時には田村さんの個展!と決めていた。
おそらく、、右へ左へとフラフラするであろう一年後
気持ちもひょっとしたら折れかけているかもしれない
一年後。ほとんど可能性は低いが、ちょこっと成功して
るかもしれない一年後・・・・
様々なことがほんの少しだけ見える一年後・・・
そのタイミングで、田村さんには“ドン”と登場してもらいたかった
のである。。。。
その個展が、いよいよ一ヵ月後にせまってきた。。。
最初の出会いから8年
まさか、方やギャラリーのプログラムディレクター
方やアーティストとして再会するなどとは・・・・
こんなワクワクする
邂逅は、、、
初めてかもしれない。。。

田村さんとの出会い 6
November 1,2009
November 1,2009
期待値商品という言葉がある。
この30年間で日本の流通業において
変化した点を考えると、やはりコンビニエンスストアー
という存在は大きい。
もちろん営業時間の24時間制もそうだが、多分、日本
独特の商品構成やシステムが多の国のコンビニエンス
ストアーとは違う側面をもっているというのが象徴的な
特徴かな?と思えるのである。
諸説あるが、コンビニの第1号は私の認識では確か昭和49年
1974年、今から35年前に出来たセブンイレブンが最初だった
と思う。
この始まりから、後発ながら他の流通業を押しのけ、今まで順調
に伸びてきた?事は誰しも疑う余地のない事実なのだが、さてここで
面白いのは、果たしてこの一号店がオープンしたとき、一番最初に
売れた商品がなんだったか?ある意味、この商品が日本における
コンビニという流通業のスタートとなり、今に至る過程を形成した
象徴的なものであったのじゃないか?なぁ、、と私は考えている。。
それは何か?
実は“サングラス”だったらしい。。。
当然、この一号店における商品構成は現在とかなり違うであろうが、
本質的な部分がそう違うということはなかった考えられる。
実際オープンして最初の販売物が“サングラス”ということは意外では
ないだろうか?
しかし、実はこの意外さが私は後々のコンビニの発展を支えたような
気がしてならないのである。
ここで最初に申し上げた
期待値商品という概念が出てくる。
この期待値商品というものの象徴は
よく思い出してもらいたいが、コンビニには何故か“ロウソク”などが
必ず隅かもしれないが陳列されている。
基本的にコンビニはデイリーであったり長くてもウィークリー対応の
商品による高回転というのが一般的な認識のような気がするのだが、
ロウソクという商品を考えた場合、平均的に一人の人間がロウソクを
使う頻度など一年のうち何回あるがろうか?
そう考えると、他の商品に比べれば明らかに回転率は落ちるどころか
論外の商品なのであり、商売的にそうも売れないもに陳列棚を占拠させ
て置く事は非常に勿体無いような気がする。
しかし全店とまでは言わないが、ロウソクないしはそれに類似するような
商品が必ずコンビニには陳列してある。
これが所謂、期待値商品と呼ばれるものなのである。
フッと考え直せばわかることなのだが、ほとんど必要ないものとして
コンビニで買うことはないのだが、認識は植え付けられている。
コンビニには“ロウソク”がある・・誰がわざわざコンビニで買うんだろう?
などというような…
これが実は大きい!
もし、自分の中で何かを探し買い求めなくてはならない状況が生まれたとき
当然、その専門店を探し向かうだろうが、そういう環境が明らかになかった
場合はどうだろうか?頭の中でどこにそういった商品があるだろうか?と
思案をめぐらせた場合、このコンビニのロウソクというのが、、、、、
ひょっとして!?
という気持ちを引っ張ってはこないだろうか?
ここが期待値商品の大きなところなのである。
ロウソクという存在が店内にあるだけで、おにぎりや雑誌その他の
商品だけで固定化してしまいがちな商売の印象をより大きく広げ、
より以上の奥行きを持たせてしまうのである。
実はこの期待値商品という概念
私はすごく参考に今もしている。
この、
考え方も実は田村さんと行なった数々の仕事の中で
教えてもらった一つだと私は認識している。
その壁の向こう!そこに何かがある。
そう思わせないと…・そういうことをする“場所”だと・・
思ってもらわないと…
なにがある?という事ばかりを拙速に伝えるのが
大事ではなく、、、、
なにかがあるかも?という部分、、
そういうイメージこそが商売にとっては
一番大事な商品なのではないかなぁ?
と、、、、今日も理想を頭の中で思い描いている…・
つづく。。
次回は一旦会社を辞められた田村さんとの
再会を書きたいと思います。。
この30年間で日本の流通業において
変化した点を考えると、やはりコンビニエンスストアー
という存在は大きい。
もちろん営業時間の24時間制もそうだが、多分、日本
独特の商品構成やシステムが多の国のコンビニエンス
ストアーとは違う側面をもっているというのが象徴的な
特徴かな?と思えるのである。
諸説あるが、コンビニの第1号は私の認識では確か昭和49年
1974年、今から35年前に出来たセブンイレブンが最初だった
と思う。
この始まりから、後発ながら他の流通業を押しのけ、今まで順調
に伸びてきた?事は誰しも疑う余地のない事実なのだが、さてここで
面白いのは、果たしてこの一号店がオープンしたとき、一番最初に
売れた商品がなんだったか?ある意味、この商品が日本における
コンビニという流通業のスタートとなり、今に至る過程を形成した
象徴的なものであったのじゃないか?なぁ、、と私は考えている。。
それは何か?
実は“サングラス”だったらしい。。。
当然、この一号店における商品構成は現在とかなり違うであろうが、
本質的な部分がそう違うということはなかった考えられる。
実際オープンして最初の販売物が“サングラス”ということは意外では
ないだろうか?
しかし、実はこの意外さが私は後々のコンビニの発展を支えたような
気がしてならないのである。
ここで最初に申し上げた
期待値商品という概念が出てくる。
この期待値商品というものの象徴は
よく思い出してもらいたいが、コンビニには何故か“ロウソク”などが
必ず隅かもしれないが陳列されている。
基本的にコンビニはデイリーであったり長くてもウィークリー対応の
商品による高回転というのが一般的な認識のような気がするのだが、
ロウソクという商品を考えた場合、平均的に一人の人間がロウソクを
使う頻度など一年のうち何回あるがろうか?
そう考えると、他の商品に比べれば明らかに回転率は落ちるどころか
論外の商品なのであり、商売的にそうも売れないもに陳列棚を占拠させ
て置く事は非常に勿体無いような気がする。
しかし全店とまでは言わないが、ロウソクないしはそれに類似するような
商品が必ずコンビニには陳列してある。
これが所謂、期待値商品と呼ばれるものなのである。
フッと考え直せばわかることなのだが、ほとんど必要ないものとして
コンビニで買うことはないのだが、認識は植え付けられている。
コンビニには“ロウソク”がある・・誰がわざわざコンビニで買うんだろう?
などというような…
これが実は大きい!
もし、自分の中で何かを探し買い求めなくてはならない状況が生まれたとき
当然、その専門店を探し向かうだろうが、そういう環境が明らかになかった
場合はどうだろうか?頭の中でどこにそういった商品があるだろうか?と
思案をめぐらせた場合、このコンビニのロウソクというのが、、、、、
ひょっとして!?
という気持ちを引っ張ってはこないだろうか?
ここが期待値商品の大きなところなのである。
ロウソクという存在が店内にあるだけで、おにぎりや雑誌その他の
商品だけで固定化してしまいがちな商売の印象をより大きく広げ、
より以上の奥行きを持たせてしまうのである。
実はこの期待値商品という概念
私はすごく参考に今もしている。
この、
考え方も実は田村さんと行なった数々の仕事の中で
教えてもらった一つだと私は認識している。
その壁の向こう!そこに何かがある。
そう思わせないと…・そういうことをする“場所”だと・・
思ってもらわないと…
なにがある?という事ばかりを拙速に伝えるのが
大事ではなく、、、、
なにかがあるかも?という部分、、
そういうイメージこそが商売にとっては
一番大事な商品なのではないかなぁ?
と、、、、今日も理想を頭の中で思い描いている…・
つづく。。
次回は一旦会社を辞められた田村さんとの
再会を書きたいと思います。。

田村さんとの出会い 5
October 31,2009
October 31,2009
田村さんにデザインしてもらった
この売り場の結果であるが、、、
最初手を加える前の数字を年商1,500万円
月商約100万強とお伝えしたと思う。
これが3年間で約3倍になった。。
当初3ヶ月は正直大した反応はなかったが
3ヶ月を越えた位から徐々に反応が出だし
あれよあれよと数字は伸びていった。。
もちろん、売り場環境だけが功を奏したとい
ワケではない。この間、悪弊に苛まれてきた
取引条件の変更、販売を担当してくれている
派遣社員のスキルアップ等の状況も好転した。
しかし、それにしても・・・
うそだぁ!そんなワケが・・・・・と言うのが
私の率直な感想で、今も多少関わりを持って
百貨店という商売を見ているが、これほどの
伸長の経験は過去20年来ない。
決してバブル華やかなりしころの数字ではない。
どちらかと言えば、デフレスパイラルなどという言葉
が世間を賑わし、不況真っ只中だった。。。
確かに売り場の環境が変われば、、という基幹的事象の創出で
あることは間違いない。例えば派遣社員にしても今までと
違う明確な売り場というゾーンが生まれると、より主体的な
責任感が生まれる。
そこで自己オペレーションをするとなると、自らの個性
というものをより具体的に発揮し出す。これはどのような
効果があるかと言えば、顧客という固定的な客層
を摑み始めるのである。特段買うものがなくても
そのお客との関係性が密になり、数ヵ月後、一年後
等の周期で買い物が発生してくる。これを何人も
作り出すと、いわゆる車のセールスのような仕組みが
動き出し、車検という一つのサイクルで商売を仕掛け
る、それと同様のようなきっかけが受動的でなく作り出し
やすくなる。
また取引条件も高回転が生まれてくれば、買取りなど
という返品リスクのある条件である必要がない。
商材供給のタイミングと量を販売員からのデーター
などにより、より精度高くコントロールでき、ロス
率は一気に逓減する。。
これらの条件も加わったことにより、よりよい形のスパイ
ラルが生れ、、1年を越えた辺りからはグイグイとこちらの
過去の想像を遥かに越える伸び率が生まれた・・・
1,500万円の3倍、4500万円、月400万円弱か・・・?
大したことないと思われる方も多々いらっしゃるかと思う。
しかし、この条件を東京、名古屋、大阪などの都市部の
スケールでみればそう思うかもしれないが一次商圏が
50万人を切るエリアで、なおかつ生活必需品としての用途
が限りなく薄い我々の商材、そしてなにより、、、、、
僅か6坪という環境・・これらを総合して考えていただければ
この数字は決して過小でないという理解をしてもらえると思
います。
しかし、、この時、田村さんのデザインだから!
という事で結論付けたワケではない。が、、、この伸長の根拠を
考えると必ず田村さんが施してくれた物理的環境との関係性が出てくる・・・
この後、何度も同じような仕事を頼んだが、100%というワケでは
ないが約80%近くは成功したと思う。。
ある時、明確に気付いた事があった。
田村さんのデザインやパース画はすごく“ロマンティック”なのだが
実際には、それを作り出す田村さんは冷徹と言えるぐらい、リアリスト
なのではないか・・・と、、、
リアリズム、我々の現実的な限界、それは資金的なものもあれば、
人的なパフォーマンスもある、また取引関係の強弱もある。それら
を長い時間毎回聞き出すわけではなく、こちらに気持ちよく喋らせ、
その間、刻々とスキャンしていたような気がしてならないのだ。
数式にて割り出され、そして美観を整え、自分のデザイン的な仕上
がり。
これで実は完結する。。
しかし実際そこには数字や自己のデザインを破棄しなくてはならない、
現実的なクライアントの制約が存在する。それを如何に融合させるか?
はい!できました・・だけでは、商売として通用するかどうか?
結果のおたのしみ!などと言うわけにはいかない・・・・
だからロマンティックなパース画に代表される表面的な部分が実は
それらのリアリズムによって細部を構成してから作られているのだ
と、売り場を活用しだしてから多々気付かされる事があった・・・
まさしく
商売の神様は細部に宿る・・・の例えの如く、表面的なデザインと
リアリズムのある細部。。その両端部分を繋ぐ堅牢さが優れたデザ
ンなのだ、、、と
これには先輩より教え込まれた
確信的な私なりの根拠もある。
私は売り場というものを訪れる時、必ず売り場を見る時間の倍は
ストックをチェックする。当然在庫状況ということもあるが、
一番は清潔さである。空間の清掃という意味もあるが、商品の陳列
状況や、ストック場所の固定化がちゃんと行われているか、空き箱
と商品が混在していないか?などである。実際、私の過去の経験から
ストック場の汚い売り場でよく売れた例がなかったのである。
ストックというお客の目に触れない場所、ここを見れば、売り場の
状況など実は手に取るようにわかる。そして実際、商売人の考え方
の表出は売り場というように捉えがちだが、実際は、ストックの
環境こそが商売人の考え方を如実に現しているのだと私は考えている。
新入社員の一番の仕事は“掃除”である。これはどのような仕事でも
同じだと思う。このお客の目に触れるだけでない、細部までを清掃する
行為こそが、仕事を覚える一番の近道であり、表面的なもてなしだけで
ない細部にわたるもてなしを“ISM”を考える一番の勉強となるよう
な気がするのだ・・
実は、こういう目に見えない環境があって
照明を浴びる売り場という華やかな存在がある。
実際その華やかさにはコントラストとしての見えない部分、、
細部があるから浮かび上がらせる事ができるのであり、それは
商品、人的、物理的環境と多岐にわたり、それぞれがコントラスト
を持っている。この両極の色彩を上手く摑めるか否か、これが
実はクライアントの意向を越え、優れたデザインを供給できるか
どうかの力量になるような気が私にはしたのと、そのためには実は
ストイックなデザイナーとしての自己抑制の効いたリアリズムが必
要なのだ
と、、、、田村さんを見て数年後、解釈したのであった。。
先述したが、この後、何回も田村さんにデザインの仕事は依頼した
現場に同行してもらい、工事までしてもらったものもあった・・
しかし、ある時、この最初の出会いとなった売り場が
突如改装という理不尽な状況に追い込まれた。。。。。。
その時を同じくして
田村さんが会社を辞た、、、
という事が耳に入ってきた・・
偶然?なのだが、出会いのきっかけとなった
売り場が、、、理不尽極まりない改装という状況を
向かえた場面で、田村さんとの仕事は一旦途切れる
こととなった、、
つづく。。
この売り場の結果であるが、、、
最初手を加える前の数字を年商1,500万円
月商約100万強とお伝えしたと思う。
これが3年間で約3倍になった。。
当初3ヶ月は正直大した反応はなかったが
3ヶ月を越えた位から徐々に反応が出だし
あれよあれよと数字は伸びていった。。
もちろん、売り場環境だけが功を奏したとい
ワケではない。この間、悪弊に苛まれてきた
取引条件の変更、販売を担当してくれている
派遣社員のスキルアップ等の状況も好転した。
しかし、それにしても・・・
うそだぁ!そんなワケが・・・・・と言うのが
私の率直な感想で、今も多少関わりを持って
百貨店という商売を見ているが、これほどの
伸長の経験は過去20年来ない。
決してバブル華やかなりしころの数字ではない。
どちらかと言えば、デフレスパイラルなどという言葉
が世間を賑わし、不況真っ只中だった。。。
確かに売り場の環境が変われば、、という基幹的事象の創出で
あることは間違いない。例えば派遣社員にしても今までと
違う明確な売り場というゾーンが生まれると、より主体的な
責任感が生まれる。
そこで自己オペレーションをするとなると、自らの個性
というものをより具体的に発揮し出す。これはどのような
効果があるかと言えば、顧客という固定的な客層
を摑み始めるのである。特段買うものがなくても
そのお客との関係性が密になり、数ヵ月後、一年後
等の周期で買い物が発生してくる。これを何人も
作り出すと、いわゆる車のセールスのような仕組みが
動き出し、車検という一つのサイクルで商売を仕掛け
る、それと同様のようなきっかけが受動的でなく作り出し
やすくなる。
また取引条件も高回転が生まれてくれば、買取りなど
という返品リスクのある条件である必要がない。
商材供給のタイミングと量を販売員からのデーター
などにより、より精度高くコントロールでき、ロス
率は一気に逓減する。。
これらの条件も加わったことにより、よりよい形のスパイ
ラルが生れ、、1年を越えた辺りからはグイグイとこちらの
過去の想像を遥かに越える伸び率が生まれた・・・
1,500万円の3倍、4500万円、月400万円弱か・・・?
大したことないと思われる方も多々いらっしゃるかと思う。
しかし、この条件を東京、名古屋、大阪などの都市部の
スケールでみればそう思うかもしれないが一次商圏が
50万人を切るエリアで、なおかつ生活必需品としての用途
が限りなく薄い我々の商材、そしてなにより、、、、、
僅か6坪という環境・・これらを総合して考えていただければ
この数字は決して過小でないという理解をしてもらえると思
います。
しかし、、この時、田村さんのデザインだから!
という事で結論付けたワケではない。が、、、この伸長の根拠を
考えると必ず田村さんが施してくれた物理的環境との関係性が出てくる・・・
この後、何度も同じような仕事を頼んだが、100%というワケでは
ないが約80%近くは成功したと思う。。
ある時、明確に気付いた事があった。
田村さんのデザインやパース画はすごく“ロマンティック”なのだが
実際には、それを作り出す田村さんは冷徹と言えるぐらい、リアリスト
なのではないか・・・と、、、
リアリズム、我々の現実的な限界、それは資金的なものもあれば、
人的なパフォーマンスもある、また取引関係の強弱もある。それら
を長い時間毎回聞き出すわけではなく、こちらに気持ちよく喋らせ、
その間、刻々とスキャンしていたような気がしてならないのだ。
数式にて割り出され、そして美観を整え、自分のデザイン的な仕上
がり。
これで実は完結する。。
しかし実際そこには数字や自己のデザインを破棄しなくてはならない、
現実的なクライアントの制約が存在する。それを如何に融合させるか?
はい!できました・・だけでは、商売として通用するかどうか?
結果のおたのしみ!などと言うわけにはいかない・・・・
だからロマンティックなパース画に代表される表面的な部分が実は
それらのリアリズムによって細部を構成してから作られているのだ
と、売り場を活用しだしてから多々気付かされる事があった・・・
まさしく
商売の神様は細部に宿る・・・の例えの如く、表面的なデザインと
リアリズムのある細部。。その両端部分を繋ぐ堅牢さが優れたデザ
ンなのだ、、、と
これには先輩より教え込まれた
確信的な私なりの根拠もある。
私は売り場というものを訪れる時、必ず売り場を見る時間の倍は
ストックをチェックする。当然在庫状況ということもあるが、
一番は清潔さである。空間の清掃という意味もあるが、商品の陳列
状況や、ストック場所の固定化がちゃんと行われているか、空き箱
と商品が混在していないか?などである。実際、私の過去の経験から
ストック場の汚い売り場でよく売れた例がなかったのである。
ストックというお客の目に触れない場所、ここを見れば、売り場の
状況など実は手に取るようにわかる。そして実際、商売人の考え方
の表出は売り場というように捉えがちだが、実際は、ストックの
環境こそが商売人の考え方を如実に現しているのだと私は考えている。
新入社員の一番の仕事は“掃除”である。これはどのような仕事でも
同じだと思う。このお客の目に触れるだけでない、細部までを清掃する
行為こそが、仕事を覚える一番の近道であり、表面的なもてなしだけで
ない細部にわたるもてなしを“ISM”を考える一番の勉強となるよう
な気がするのだ・・
実は、こういう目に見えない環境があって
照明を浴びる売り場という華やかな存在がある。
実際その華やかさにはコントラストとしての見えない部分、、
細部があるから浮かび上がらせる事ができるのであり、それは
商品、人的、物理的環境と多岐にわたり、それぞれがコントラスト
を持っている。この両極の色彩を上手く摑めるか否か、これが
実はクライアントの意向を越え、優れたデザインを供給できるか
どうかの力量になるような気が私にはしたのと、そのためには実は
ストイックなデザイナーとしての自己抑制の効いたリアリズムが必
要なのだ
と、、、、田村さんを見て数年後、解釈したのであった。。
先述したが、この後、何回も田村さんにデザインの仕事は依頼した
現場に同行してもらい、工事までしてもらったものもあった・・
しかし、ある時、この最初の出会いとなった売り場が
突如改装という理不尽な状況に追い込まれた。。。。。。
その時を同じくして
田村さんが会社を辞た、、、
という事が耳に入ってきた・・
偶然?なのだが、出会いのきっかけとなった
売り場が、、、理不尽極まりない改装という状況を
向かえた場面で、田村さんとの仕事は一旦途切れる
こととなった、、
つづく。。