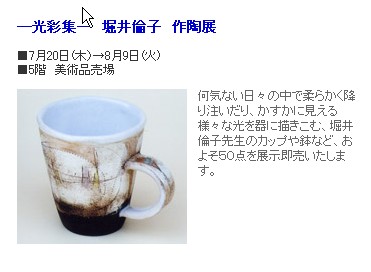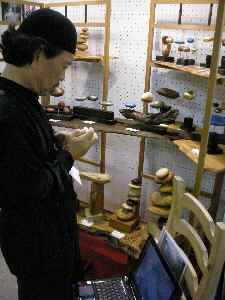August 3,2011
「放射能が降っています。静かな、静かな夜です。」
ある日京都新聞を読んでいてこの一節が目に留まり、、
”ハッ”とした!
ご存知の方も多いと思いますが、福島在住の詩人
和合亮一さんの詩の一節であり、現在も彼はtwitterで
「震災詩」を展開している。
この日読んだこの一節を含む記事とは
「京都新聞・現代のことば」で現京都市立芸術大学学長
で美術評論家の建畠哲氏の「震災と詩人」というコラムで
あった。
アウシュビッツの後に、詩を書くのは野蛮だと述べたのは、
ドイツの哲学者、テオドール・アドルノである。
という一文から始まるコラムであり、現在の震災、及び
その中で生きる詩人とテオドールを重ねて論旨を構築し
ているのだが、もっとも交差するポイント・野蛮という
意味を和合氏のtwiiterでのつぶやきから抽出する。
「こんなことってあるのか比喩が死んでしまった」
確かに、大きく感じ頷けるものがある。
どんな比喩を駆使しようとも、、現実の持つ大きさ、、、、
この国ではそれをインスタントに「想定外」と安売りして
いるが、いずれにしても詩人がその惨状を他者に表現しよ
うとしても比喩となるその言葉には空虚さと欺瞞しか滲み
出さないし現時点で聞くものの心に重なり合い何らかの感
情の増幅が働くような響きはないだろう。
それどころか、、、
確かに、他人事のように聞こえてしまいかねない言葉の
選択は、、苦渋を味わう人間からすれば”暴力”に等しく
即ち”野蛮”な行為と化す。
言葉がない、とは正しくの状態である。。
詩人にとって言葉がない状態とは・・と考えたとき
失礼ながら詩人と呼ばれる人が詩をもって生業と
していけている人がいかほどいるのだろうか?
現実には皆無に近いのではないだろうか?
そう考えると、詩人とは職業ではなく、ある意味
生き方の種別、それもかなり純度の高い種類
になるのではないだろうか?
どういった純度かと考えれば、人間そのものを概
念化させる、つまり全ては自己の中にある他人と
いう存在の自分、、、、、
(通念としてはあくまでも他人であるが、その他人
という概念の本質は自ら作り出した他者でしか
ない。他人などというものは肉体の視覚的認知
以外本質的な概念化は自己の中で創出している
他人という自分でしかない)
と、この他人という想定から観る自分という存在、
またその存在関係の倍数的存在の社会という
構造、その違いを整理し、消滅するまですり合わせ
空洞と化した自分を作り出す、その空洞と化した
自分の真ん中を言葉という感覚の最大公約数に
翻訳する作業で突き抜かせる、詩人とは、その
言葉の濃度と純度が著しく高い人種のような気が
するのである。
その詩人にとって存在の全てである言葉がなくなる
というのは死にも値する。。
しかしここで建畠哲氏はあえて逆説的にこの死
こそが的確な比喩と化したと解説する。
付け加えて、、、、、こうも解説する、、、
震災は一人の詩人から比喩を奪ってしまった。
だが彼は比喩の死という事態を正しく見据え、
その”静かな夜”に一人佇み、黙礼する。
それもまた詩人の姿なのだ・・・・と、、、、
「放射能が降っています。静かな、静かな夜です。」
詩人はそのまま伝えている。
この一節に言葉としての比喩はない。
しかし、、、、
涙が止めどなく溢れてくる・・・・・・・・
---------
私はハッと気づかされ
符合する時代感覚を改めて認識する。
これは詩人という芸術家の存在だけの話なのだろうか?
違う全ての芸術家は皆同じであり、、、、、
そういう時代の幕開けに突入したのだと私は感じている。
今いる芸術家、20代から存在すると考えても
この先50年、半世紀への大きな幕開け、転換点
なのではないか?と感じている。
転換するという事は、その以前は雲散霧消とまでは
言わないが、ほぼ通用しなくなる。当然通用しなくなる
という理由は歴然としている。
涙が止めどなく溢れるような
感覚の相違からくるわけであり、前述を引用すれば、以
前における比喩は死に、新たな逆説的比喩、ともすれ
ば捨て身の比喩=詩人の純度=芸術家としての純度
これら全てはどのアイデンティーから生じ?どこに向かって
発露されるのかが想像以上必要となると私は感じてい
るのと同時に、、、、、
求めていかなければいけない!と考えている!
今日!
日本の芸術家には明確に求められているものがある!
ある日京都新聞を読んでいてこの一節が目に留まり、、
”ハッ”とした!
ご存知の方も多いと思いますが、福島在住の詩人
和合亮一さんの詩の一節であり、現在も彼はtwitterで
「震災詩」を展開している。
この日読んだこの一節を含む記事とは
「京都新聞・現代のことば」で現京都市立芸術大学学長
で美術評論家の建畠哲氏の「震災と詩人」というコラムで
あった。
アウシュビッツの後に、詩を書くのは野蛮だと述べたのは、
ドイツの哲学者、テオドール・アドルノである。
という一文から始まるコラムであり、現在の震災、及び
その中で生きる詩人とテオドールを重ねて論旨を構築し
ているのだが、もっとも交差するポイント・野蛮という
意味を和合氏のtwiiterでのつぶやきから抽出する。
「こんなことってあるのか比喩が死んでしまった」
確かに、大きく感じ頷けるものがある。
どんな比喩を駆使しようとも、、現実の持つ大きさ、、、、
この国ではそれをインスタントに「想定外」と安売りして
いるが、いずれにしても詩人がその惨状を他者に表現しよ
うとしても比喩となるその言葉には空虚さと欺瞞しか滲み
出さないし現時点で聞くものの心に重なり合い何らかの感
情の増幅が働くような響きはないだろう。
それどころか、、、
確かに、他人事のように聞こえてしまいかねない言葉の
選択は、、苦渋を味わう人間からすれば”暴力”に等しく
即ち”野蛮”な行為と化す。
言葉がない、とは正しくの状態である。。
詩人にとって言葉がない状態とは・・と考えたとき
失礼ながら詩人と呼ばれる人が詩をもって生業と
していけている人がいかほどいるのだろうか?
現実には皆無に近いのではないだろうか?
そう考えると、詩人とは職業ではなく、ある意味
生き方の種別、それもかなり純度の高い種類
になるのではないだろうか?
どういった純度かと考えれば、人間そのものを概
念化させる、つまり全ては自己の中にある他人と
いう存在の自分、、、、、
(通念としてはあくまでも他人であるが、その他人
という概念の本質は自ら作り出した他者でしか
ない。他人などというものは肉体の視覚的認知
以外本質的な概念化は自己の中で創出している
他人という自分でしかない)
と、この他人という想定から観る自分という存在、
またその存在関係の倍数的存在の社会という
構造、その違いを整理し、消滅するまですり合わせ
空洞と化した自分を作り出す、その空洞と化した
自分の真ん中を言葉という感覚の最大公約数に
翻訳する作業で突き抜かせる、詩人とは、その
言葉の濃度と純度が著しく高い人種のような気が
するのである。
その詩人にとって存在の全てである言葉がなくなる
というのは死にも値する。。
しかしここで建畠哲氏はあえて逆説的にこの死
こそが的確な比喩と化したと解説する。
付け加えて、、、、、こうも解説する、、、
震災は一人の詩人から比喩を奪ってしまった。
だが彼は比喩の死という事態を正しく見据え、
その”静かな夜”に一人佇み、黙礼する。
それもまた詩人の姿なのだ・・・・と、、、、
「放射能が降っています。静かな、静かな夜です。」
詩人はそのまま伝えている。
この一節に言葉としての比喩はない。
しかし、、、、
涙が止めどなく溢れてくる・・・・・・・・
---------
私はハッと気づかされ
符合する時代感覚を改めて認識する。
これは詩人という芸術家の存在だけの話なのだろうか?
違う全ての芸術家は皆同じであり、、、、、
そういう時代の幕開けに突入したのだと私は感じている。
今いる芸術家、20代から存在すると考えても
この先50年、半世紀への大きな幕開け、転換点
なのではないか?と感じている。
転換するという事は、その以前は雲散霧消とまでは
言わないが、ほぼ通用しなくなる。当然通用しなくなる
という理由は歴然としている。
涙が止めどなく溢れるような
感覚の相違からくるわけであり、前述を引用すれば、以
前における比喩は死に、新たな逆説的比喩、ともすれ
ば捨て身の比喩=詩人の純度=芸術家としての純度
これら全てはどのアイデンティーから生じ?どこに向かって
発露されるのかが想像以上必要となると私は感じてい
るのと同時に、、、、、
求めていかなければいけない!と考えている!
今日!
日本の芸術家には明確に求められているものがある!