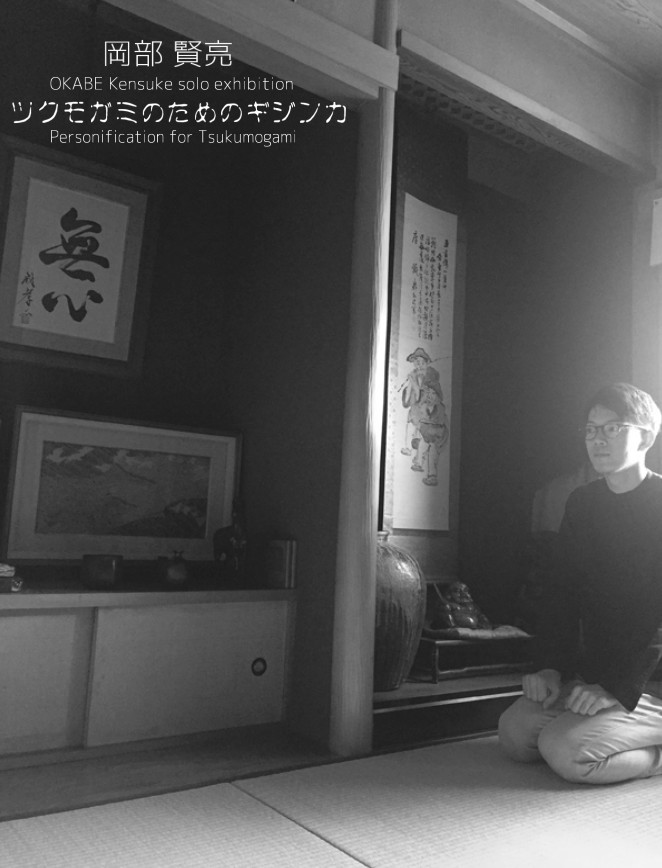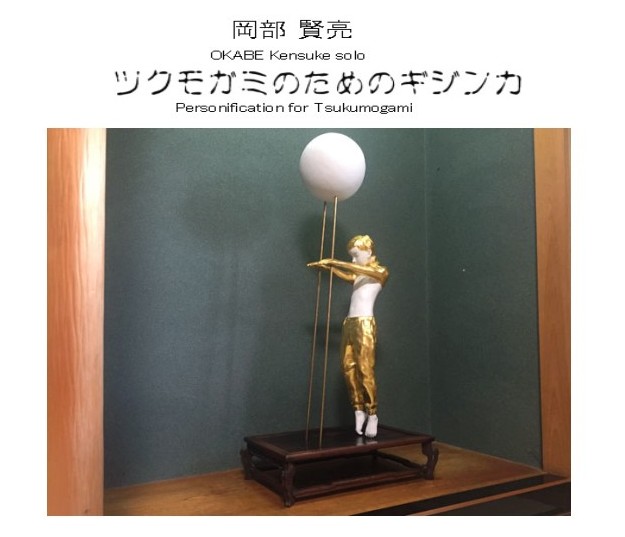October 31,2016
今週3日(木・祝)から
BAMI galleryでは、太田夏紀 『息物』
を開催いたします。

2016.11.03 (thu) - 2016.11.13 (sun)
OPEN : 12:00-18:00
期間中無休

約1年近く前、BAMI galleryでは小橋君の個展を
開催していました。その時、ひょっこり現れたのが
太田さんでした。
私は、ギャラリーの企画中、その時々の雰囲気とい
うか空気如何ではあるのですが、出来る限り来てく
れた若い人には声をかけるようにしています。大抵
そのような若者は物づくりをしている確率が高いか
らでもあるからです。
特にその時の企画であった小橋君の作品は焼物に
よる虫を制作しており、同じ道を志す若い人も
沢山来てくれていました。
が、、、、、、
この太田さんは、、、、

一際他の若い人とは違いました。。。
まず、、、その滞在時間・・・・
おそろしく長かったような記憶があります。
凝視している所に声をかけても悪いので、
見終わるまで待っていましたが、、、、
なかなか終わらない。。。
それと、、あっちいったりこっちいったり・・
少なからず、、挙動が不審でした。。。
変わった子だなぁ~と、、、、ギャラリーに来る、
若い女の子も沢山見てきたのですが、、一際異彩を
放っていたようにその時は感じました。
見終わったかな?という頃合で声をかけると、
やはり焼物をやっていて、当方の遠藤君の後輩だと
言う事でした。早速、どんな物を作っているのか
見せてもらったのですが、うん??悪くはない??
年齢を聞くと、、、23歳・・・・
なっ、なんと、、私の娘と同い年ではないか。。。
正直、、、悪くはないのだが、、自分の娘を下敷きに
考えたとき、、作家?もしくは作家になっていく??
というイメージのギャップというのか違和感があった。
うーん、、、確かに作品が良ければ、、、
八木くんとの最初の出会いも彼が19歳かそこらだった
ような記憶がある・・・・
ただ、、私にとって太田さんのその時の最大の印象は
作品もさることながら、、長らく剣道をやっていた
という事もあるのか、比較的何を言っても受け留める、、
つまり、私は若い人に対してはかなりキツイ言葉と内容
をぶつける。ある意味こき下ろす。
ただそれは、私なりの礼儀でもある。せっかく来てくれ
たのだから、彼ら彼女達の甘い部分を粉々に粉砕し、
大学とは違う、私が考える現実と各自の作品の程度の低さを
感受してもらおうと・・・・
まぁ、、どう受け止めるかは其々次第なのだが、、
大抵は嫌われているだろう・・・
戻るが、太田さんにも同じようにキツイ事を言った
筈なのだが、、あれっ??と言うくらい、、強い!
この子のこの強さ・・・
これが私が一番印象に残った事でした。。。
その後、確か何度か?来てくれたように記憶していますが、
毎度の事で記憶が曖昧・・・
ただ何時だったかハッきりとは記憶していないが、、
精華-ESSENCE 展という精華の現役学生と卒業生を対象に
した企画を公募で行おうと立案した時に、良かったら
応募してとだけ告げたのを覚えています。
誘ったのだが、正直忘れていて、、
さて、公募の作品を選ぶという段になり、あっ!
応募してくれたのだと気付きました。
ただ、精華-ESSENCE 展の公募審査は、先ずは
釜くん松本くん遠藤くん宮本くんに任せており
最終で私が判断するという仕組みにしていたので
応募してきたのは分かっていたのですが、黙って
いましたが、、、最初の審査でダントツの選択でした。
さて、そこから私は今回の個展企画をスタートさせた
のです。6月ごろ、、約半年前、、
8月終わりか9月初めに個展の諸々の打ち合わせレジュメを
渡し、何度か打ち合わせを行ったのですが、、、、
当然はじめての個展で戸惑う事も多かったと思いますが、
私にとって、この個展の最大のポイントは、、、、
彼女が何をしたいのか?
という事でした。
当然生き物の造形を陶芸で行うのですが、それよりも
なぜそれが陶芸で生き物でないと自身の必然がうまれ
ないのか?という事でした。勿論明確な文書化などは
必要ありません。しかし、学校の課題のように一点
一点を作り評価を仰ぐのとは個展は訳が違います。

ただ単に台の上に乗せて”良く出来ている?”という
事となど、私のギャラリーでは意味をなさないし、
その程度のことなら私がやる必要もない。

その点をどう理解し、形に現すのか?
何度かその事を集中的に話し合いました。

今回のステートメントが出来上がった時、何となく
ではあるのですが、この子の持っている魅力みたいな
ものが、ほんのりと香って来ました。それと同時に
私が常々考えている事とのリンク箇所が心地よかった。
***********
人に慣れていて危害を加えない生き物と一緒に生活
することは、私たちにとって都合の良いことが多い。
例えば、ペットとして、家畜として…野生ではない
生き物達は、「人間以外の生き物」として所有され、
人間の生活に私達の都合で、強制的に共に生活をする
事となる。生き物達が自分の生きたい様に生きられず
に、不自由な生活に息苦しさを感じているとわかって
いても、人間は生き物に対して一方的に愛情を注ぎ、
利用する。
外で走り回りたいと思っている犬を「逃げた」と言っ
て家の中に連れ戻したり、卵を産むために鶏は狭い
小屋に入れられる。そうして、外敵に襲われる事の無い、
安全で不自由な人間の世界に閉じ込められるのだ。
しかし、そんなことを知りながら悪気も無く、可愛いと
か大切だとか、人間のエゴだとわかっていながら愛おし
いと思ってしまう。 人間に逆らう事無く、静かにしっ
かりと息をしている生き物達を、「息物」として、
焼き物で表現したい。
*********
人間のエゴだとわかっていながら

この生き物との対峙が凄く気に入りました。
北野武の言葉

「よく生きがいっていうんだけど、
生きがいなんてそんな大切なもんかね。」
生きがいとは一般的に
人生の意味や価値など,人の生を鼓舞し,その人の
生を根拠づけるものを広く指す。〈 生きていく上での
はりあい〉といった消極的な生きがいから,〈人生い
かに生くべきか〉といった根源的な問いへの〈解〉と
してのより積極的な生きがいに至るまで,広がりがある。
まぁ恐らく上記の様な意味が通念であり、
ごく普通の社会生活を送ってきたものからすれば
ある意味、金科玉条のように心に張り付いている言葉
だろう。
しかし、生き物、、犬や猫は何のために生きているの
と問えば、、どう答えるのだろうか?


生きがいとは人間独自のモノということだろうが、
もっとも根源的な命という所の線上で考えれば
犬や猫も我々も同じ生き物である。

そう考えたとき、北野武が言っている事の意味が
おぼろげながら感じてくる。
●生きていく上でのはりあい
●人生いかに生くべきか
それよりも、生きるために生きる

生き物は総じてそうじゃないのか?と感じる。
先般、障害者施設に入り大量殺人を犯した輩が
「生きていく価値がない」と言ったと聞きます。
生きていく価値???

生きるために生きる生き物にそんな価値判断が
ある訳がない・・・・
すべて、何か間違ったエゴなのじゃないか?

しかし、そのエゴを抱えているのが人間であり
そして、そのエゴとの距離、埋めることのできない
距離を持っているのが我々の周りの生き物たち
じゃないのか?
人間どうしですら・・・
と考えさせられる・・・・・
-------------
人間のエゴだとわかっていながら・・・・
------------
”息物”と銘打った今回の個展
太田夏紀の作品から
今回そして今後、様々なものをぜひ感じて欲しいと
願うのと同時に、この初個展を最初にドンドン成長
して欲しいと私は念じています。

BAMI galleryでは、太田夏紀 『息物』
を開催いたします。

2016.11.03 (thu) - 2016.11.13 (sun)
OPEN : 12:00-18:00
期間中無休

約1年近く前、BAMI galleryでは小橋君の個展を
開催していました。その時、ひょっこり現れたのが
太田さんでした。
私は、ギャラリーの企画中、その時々の雰囲気とい
うか空気如何ではあるのですが、出来る限り来てく
れた若い人には声をかけるようにしています。大抵
そのような若者は物づくりをしている確率が高いか
らでもあるからです。
特にその時の企画であった小橋君の作品は焼物に
よる虫を制作しており、同じ道を志す若い人も
沢山来てくれていました。
が、、、、、、
この太田さんは、、、、

一際他の若い人とは違いました。。。
まず、、、その滞在時間・・・・
おそろしく長かったような記憶があります。
凝視している所に声をかけても悪いので、
見終わるまで待っていましたが、、、、
なかなか終わらない。。。
それと、、あっちいったりこっちいったり・・
少なからず、、挙動が不審でした。。。
変わった子だなぁ~と、、、、ギャラリーに来る、
若い女の子も沢山見てきたのですが、、一際異彩を
放っていたようにその時は感じました。
見終わったかな?という頃合で声をかけると、
やはり焼物をやっていて、当方の遠藤君の後輩だと
言う事でした。早速、どんな物を作っているのか
見せてもらったのですが、うん??悪くはない??
年齢を聞くと、、、23歳・・・・
なっ、なんと、、私の娘と同い年ではないか。。。
正直、、、悪くはないのだが、、自分の娘を下敷きに
考えたとき、、作家?もしくは作家になっていく??
というイメージのギャップというのか違和感があった。
うーん、、、確かに作品が良ければ、、、
八木くんとの最初の出会いも彼が19歳かそこらだった
ような記憶がある・・・・
ただ、、私にとって太田さんのその時の最大の印象は
作品もさることながら、、長らく剣道をやっていた
という事もあるのか、比較的何を言っても受け留める、、
つまり、私は若い人に対してはかなりキツイ言葉と内容
をぶつける。ある意味こき下ろす。
ただそれは、私なりの礼儀でもある。せっかく来てくれ
たのだから、彼ら彼女達の甘い部分を粉々に粉砕し、
大学とは違う、私が考える現実と各自の作品の程度の低さを
感受してもらおうと・・・・
まぁ、、どう受け止めるかは其々次第なのだが、、
大抵は嫌われているだろう・・・
戻るが、太田さんにも同じようにキツイ事を言った
筈なのだが、、あれっ??と言うくらい、、強い!
この子のこの強さ・・・
これが私が一番印象に残った事でした。。。
その後、確か何度か?来てくれたように記憶していますが、
毎度の事で記憶が曖昧・・・
ただ何時だったかハッきりとは記憶していないが、、
精華-ESSENCE 展という精華の現役学生と卒業生を対象に
した企画を公募で行おうと立案した時に、良かったら
応募してとだけ告げたのを覚えています。
誘ったのだが、正直忘れていて、、
さて、公募の作品を選ぶという段になり、あっ!
応募してくれたのだと気付きました。
ただ、精華-ESSENCE 展の公募審査は、先ずは
釜くん松本くん遠藤くん宮本くんに任せており
最終で私が判断するという仕組みにしていたので
応募してきたのは分かっていたのですが、黙って
いましたが、、、最初の審査でダントツの選択でした。
さて、そこから私は今回の個展企画をスタートさせた
のです。6月ごろ、、約半年前、、
8月終わりか9月初めに個展の諸々の打ち合わせレジュメを
渡し、何度か打ち合わせを行ったのですが、、、、
当然はじめての個展で戸惑う事も多かったと思いますが、
私にとって、この個展の最大のポイントは、、、、
彼女が何をしたいのか?
という事でした。
当然生き物の造形を陶芸で行うのですが、それよりも
なぜそれが陶芸で生き物でないと自身の必然がうまれ
ないのか?という事でした。勿論明確な文書化などは
必要ありません。しかし、学校の課題のように一点
一点を作り評価を仰ぐのとは個展は訳が違います。

ただ単に台の上に乗せて”良く出来ている?”という
事となど、私のギャラリーでは意味をなさないし、
その程度のことなら私がやる必要もない。

その点をどう理解し、形に現すのか?
何度かその事を集中的に話し合いました。

今回のステートメントが出来上がった時、何となく
ではあるのですが、この子の持っている魅力みたいな
ものが、ほんのりと香って来ました。それと同時に
私が常々考えている事とのリンク箇所が心地よかった。
***********
人に慣れていて危害を加えない生き物と一緒に生活
することは、私たちにとって都合の良いことが多い。
例えば、ペットとして、家畜として…野生ではない
生き物達は、「人間以外の生き物」として所有され、
人間の生活に私達の都合で、強制的に共に生活をする
事となる。生き物達が自分の生きたい様に生きられず
に、不自由な生活に息苦しさを感じているとわかって
いても、人間は生き物に対して一方的に愛情を注ぎ、
利用する。
外で走り回りたいと思っている犬を「逃げた」と言っ
て家の中に連れ戻したり、卵を産むために鶏は狭い
小屋に入れられる。そうして、外敵に襲われる事の無い、
安全で不自由な人間の世界に閉じ込められるのだ。
しかし、そんなことを知りながら悪気も無く、可愛いと
か大切だとか、人間のエゴだとわかっていながら愛おし
いと思ってしまう。 人間に逆らう事無く、静かにしっ
かりと息をしている生き物達を、「息物」として、
焼き物で表現したい。
*********
人間のエゴだとわかっていながら

この生き物との対峙が凄く気に入りました。
北野武の言葉

「よく生きがいっていうんだけど、
生きがいなんてそんな大切なもんかね。」
生きがいとは一般的に
人生の意味や価値など,人の生を鼓舞し,その人の
生を根拠づけるものを広く指す。〈 生きていく上での
はりあい〉といった消極的な生きがいから,〈人生い
かに生くべきか〉といった根源的な問いへの〈解〉と
してのより積極的な生きがいに至るまで,広がりがある。
まぁ恐らく上記の様な意味が通念であり、
ごく普通の社会生活を送ってきたものからすれば
ある意味、金科玉条のように心に張り付いている言葉
だろう。
しかし、生き物、、犬や猫は何のために生きているの
と問えば、、どう答えるのだろうか?


生きがいとは人間独自のモノということだろうが、
もっとも根源的な命という所の線上で考えれば
犬や猫も我々も同じ生き物である。

そう考えたとき、北野武が言っている事の意味が
おぼろげながら感じてくる。
●生きていく上でのはりあい
●人生いかに生くべきか
それよりも、生きるために生きる

生き物は総じてそうじゃないのか?と感じる。
先般、障害者施設に入り大量殺人を犯した輩が
「生きていく価値がない」と言ったと聞きます。
生きていく価値???

生きるために生きる生き物にそんな価値判断が
ある訳がない・・・・
すべて、何か間違ったエゴなのじゃないか?

しかし、そのエゴを抱えているのが人間であり
そして、そのエゴとの距離、埋めることのできない
距離を持っているのが我々の周りの生き物たち
じゃないのか?
人間どうしですら・・・
と考えさせられる・・・・・
-------------
人間のエゴだとわかっていながら・・・・
------------
”息物”と銘打った今回の個展
太田夏紀の作品から
今回そして今後、様々なものをぜひ感じて欲しいと
願うのと同時に、この初個展を最初にドンドン成長
して欲しいと私は念じています。

COMBINE 太田夏紀 Ceramic Works 息物 プレスリリース by COMBINE on Scribd