April 8,2009
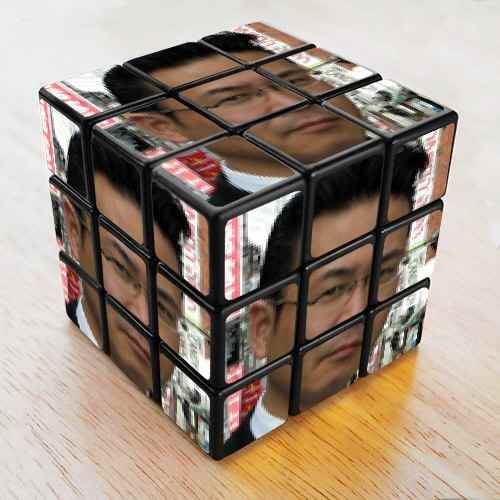
4月5日(日)
商用で岡山県倉敷市に行く。

2年ぶりである。
11時に待ち合わせ、14時打ち合わせが終了、その後特に予定はなかったのだが、久しぶりに大原美術館へ行こうと一人テクテクと倉敷美観地区へ
美観地区へ入ると桜の季節もあり大勢の観光客・・・・
当然であるがスーツにネクタイなどという”いでたち”は
我のみ・・・・
。。。。。。。。。
しかし、桜満開!実に気持ちが良い!

大原美術館

今回もともと商談終了後には訪れたいという気持ちがあった。
この美術館は
倉敷の実業家大原孫三郎(1880年–1943年)が、自身がパトロンとして援助していた洋画家児島虎次郎(1881年–1929年)に託して収集した西洋美術、エジプト・中近東美術、中国美術などを展示するため、1930年に開館した。西洋美術、近代美術を展示する美術館としては日本最初のものであり、第二次大戦後、日本にも西洋近代美術を主体とした美術館が数多く誕生したが、日本に美術館というもの自体が数えるほどしか存在しなかった昭和初期、一地方都市にすぎなかった倉敷にこのような美術館が開館したのは画期的なことであり、ニューヨーク近代美術館の開館が1929年であったことを考えれば、創設者大原孫三郎の先見性は特筆すべき・・・・
と言うのが一般的であり、誰も疑うことのない大原美術館の説明となろう。
しかし、、私にとってこの美術館の特筆すべき点とは、その歴史的なものもさるこながら、現代美術の館臓品の秀逸さが群を抜いているという点を強く推したい!
特に1950年代から1980年代にかけての日本の現代美術史にとって欠かすことのできないないアーティストの作品、及びそれら作家の現代美術史におけるエポックメーキングな作品の数々には瞠目する。
数年前、大原美術館も見とかないとな・・・っていう程度で訪れ、一般によく知られたエルグレコや民芸運動の作品群(棟方等)を見てへぇーっと当たり前に関心していたのであるが、ある空間に入った途端・・・・心臓がとまるほどの驚きを覚えた・・・・・・・
河原温 斎藤義重 荒川修作 吉原治良 季禹煥・・・・
なっ、、なんと。。。
河原温 黒人兵 1955年 油彩,画布 164×201
などは私が20歳頃、雑誌の小さなカットで何度も
何度も見つめていた作品ではないか・・
これほどの作家と作品を、、と息を飲んだ。。
そう今でこそ現代美術マーケットやオークションなどをにぎわす作家たちであり、ともすれば銘柄としてすこし時代を踏んだものになりつつあるが、高い人気で許容されている。
しかし、当時大半が見向きもしないこれらの作品を体系的にしかも密に収集してきたという事実、この冒険心、その当時(70年代前後)のこれら作家の国内での評価と”美術館として見せる”ということを前提として考えた場合の当時の入館者の反応は想像に難しくない・・・またビジネス的に考えてもこれらのコレクションを当時の日本の、しかも私立美術館が行うというのは、、二の足どころか・・・
それをよくここまでと驚愕した。。
何度も言うが今なら当たり前として考えられるし、許容もできる
しかし、ほんの数年前の現代美術の取り扱われ方を知る者からして
ましてやその何年も前のこととして考えた場合、、、
・・・・・・・・・・・・・・
今、国内有数の美術館として存在する大原美術館。
しかし、開館当初は一日の来館者ゼロという日もあったほど注目度は低かったらしい・・
創設者大原孫三郎の先見性とは、過去の事績だけのことではなく、死して尚そのスピリットが後進に何年にもわたり受け継がれていること、そこに信念の最大が存在すると改めて考えさせられた。。。


