February 7,2010
田村さんのSTONE・高松の展開に際して
事前に田村さんには細かい注文を出し
高松まで同行してもらい設営もお願いしたのですが、
実は今回の同行は、その展開設営だけが目的ではなく
もう一つ田村さんとの計画?がありました。
以前より”直島”に一緒に行きましょう!と約束して
おり、今回ようやく実現させることができたのでした。
直島行き!
それは今後の田村さんの制作活動には必ず大きな刺激に
なると確信するところであり、ひいては私どもの今後の
展開にも大きなメリットがある事であり、是非とも一緒に
行こうとかなり以前から話し合っていたのでした。。
私も、一年ぶりで、少し確認したい事もあり。。。。。
と、、言うわけで今回は”直島行き”レポートのような
始まりなのですが、、
それは次回・・・
今回は、直島行きの前日に田村さんとご一緒した
香川県丸亀市の丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(MIMOCA)
へ行ったレポートです。


実はこの美術館も田村さんには見ていただきたかったの
です。

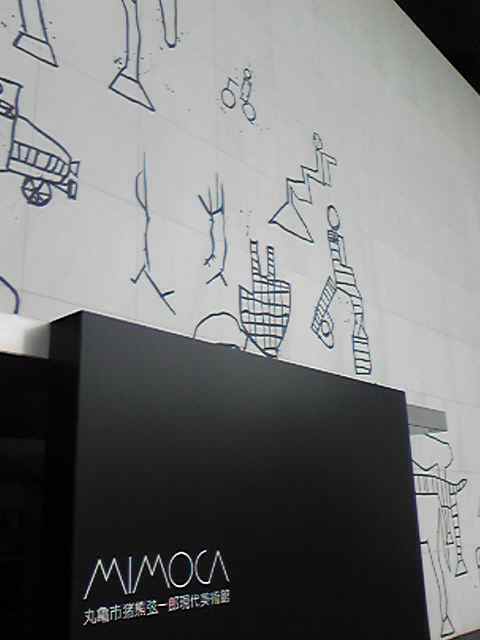
私は、このブログで再々香川県の特殊性を書いてきたと
思うのですが・・・(そうでもないかな??)
ひょんな事で行き出して丸9年、今年は10年目になる
のですが、初期、この四国北東部の、、このエリアは何故
これほど現代美術というのか先進的なアートに敏感なのか?
不思議でしょうがなく、それは今も続く感覚で明確な答え
といえるものはないのですが、確実なる一つがあるとする
ならば、この猪熊弦一郎というアーティストがこの地域の
出身で、斬新なアートの先達であったこととの関係が深い
事だけは確信しうる事実かなと思う。


他人に言わせると、何故君は高松ばかり行くの?となるが
私としては、今のこの仕事、もし仮にこの世界、特に先進
的な芸術を模索する世界に身を置いていて、なぜ行かない
の?と逆に聞き返したくなる、、のである。
という事でその話はまた後日じっくりするとして、、
先ず今回の丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(MIMOCA)訪問に
さいして一つ伝えたいのは、、
じっくり良く考えていただきたいのですが、昨今様々な
事業仕訳等の行政の無駄をスリム化する世相にあって決し
て人口が多い街でもなければ、到底都会に比べ資金力が
あるとは思えない、一地方都市、それも小さな街が、市営
でこのような難解な現代美術館を硬派にも運営し続けてい
るというのは驚愕と同時に称賛に値することを認識してい
ただきたい。東京名古屋大阪広島福岡であればさほど不思
議はない、まぁ少し譲って金沢・茨城・・・
※京都などはダラシナイ代表選手だ・・
しかし、、、、
丸亀市でこの内容!これは改めてスゴイと言わざるを得ない。
市営ということは議会で決をとり税金で運営している訳で、
市民納得の上という事であり・・


現代美術=訳の分からん?などという感性では無いのだ!

この一事を考えてもこのエリアの特異な感性に興味を持ち
続けるのはまったく不思議はないだろう。。
--------------------------------------------------
田村さんともこの事を様々話をし大いに盛り上がりました。
さて美術館ですが、さすが田村さんはもともとインテリア
や商業施設のデザイナーだけあり、我々とは見方が違い、
先ず美術館の建築から細かく見ておられました。。
こういう方と一緒に行くというのは、こういった部分で
私としても実に刺激的であり、今まで知らなかったこと
を実地で教えてもらい大いに勉強になるのでした・・
肝心の展覧ですが、残念ながらほぼ常設展に近く、猪熊
作品の色をテーマとした展覧でしたが、それはそれなりに
面白く時間をかけて二人展観いたしました・・・・・
が、、、、、、、、
実は残念どころか!!!!!
すごいモノに出会いました・・・
まったく知らなかったのですが、、
美術館の正面玄関に猪熊展以外にもう一つ??
Focus3 高嶺 格:スーパーキャパシターズ
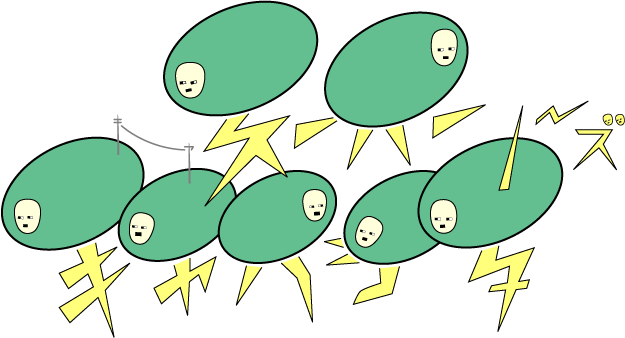
なんじゃ?こりゃ?
と、あまり期待せず覗いたのですが・・・
電撃が身体を突き抜けました。。。。
ここで美術館のステートメントを転載いたしますが
-----------------------------------------------------
以下、Focus3 高嶺 格:スーパーキャパシターズ
丸亀市猪熊弦一郎現代美術館ステートメント。
現代に鋭い視線を向けるアーティストの珠玉の作品に焦点を
絞って紹介する個展シリーズ“Focus”の第3弾です。
今回は、社会の抱える様々な矛盾や軋轢を、自分自身の問題
としてとらえ、正面から向き合って考えることから作品を生
み出し続けているアーティスト、高嶺格(たかみねただす/
1968年鹿児島県生まれ)の作品「スーパーキャパシターズ」
をご紹介します。
「スーパーキャパシタ」とは、市販されている蓄電装置の名前
です。乾電池やバッテリーに比べ、安価で安心な素材で製造で
きる上、劣化しにくく長期にわたって繰り返し使用できるとい
った画期的な性質を備えています。代替エネルギーへの取り組
みが急がれる昨今、このキャパシタや太陽電池をはじめとして、
持続可能性を視野に入れた新技術の研究開発が盛んに行われて
いますが、一方で、このような技術や考え方が確立されたとし
ても、それが市場の中で既存の技術と入れ替わるまでには、か
なり時間がかかってしまうという問題があります。いいはずの
ものがなかなか普及できない、高嶺はこのジレンマに注目し、
美術の力をもって普及の加速化を試みます。すなわち、これら
新技術にイメージを与え、ブランド化を仕掛けることで、一刻
も早い低価格化を目論むのです。2008年スタートした(*)
高嶺の「スーパーキャパシタ」キャンペーンは、その後の技術
革新も反映し、新たなアイテムをつけ加えて、2010年さらなる
拡張を図ります。
※“Focus”について
MIMOCA(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館)の2階展示室フロ
アの一室を使った展覧会シリーズで、MIMOCAがピックアッ
プした国内外で活躍するアーティストの珠玉の作品をご紹介する
ものです。
本展は、2006年開催の「スティーヴ・マックィーン[Caresses]」、
2008年開催の「エイヤ=リーサ・アハティラ展」につづく、第3
回展となります。
--------------------------------------------------------
展覧自体の風景は
所謂、無機質なミニマルアート的ではあるのですが・・・・
私が電撃を受けたというのは、このコンセプトです。
今後の現代美術と呼ばれるものが向かう、特に日本の
現代美術が突き抜けていく一つの大きな方向性が漠然と
ではありますが、この作家の示す方向ではないか?と
感じたのでした・・
このコンセプトは必ず大きな芸術的概念化を遂げ
世界に向けた大きな潮流となる。
特に
いいはずのものがなかなか普及できない、高嶺はこの
ジレンマに注目し、美術の力をもって普及の加速化を
試みます。
という部分・・・
今世界的に様々な分野が閉塞感に苛まれている現代、
全てにおいて循環に破綻が差し迫っている世紀
・・・苦しい逆境の中で、、、
乗り越えなくてはならない現実
その為の人間哲学、科学技術、、、、等々
我々は新たな人間生活を社会を循環させていく為に
新たな論理を生み出さなくてはならない。
それは、”排除”の論理ではなく”共生”の論理で
あり、その根幹となる人間感性の刺激は、、
やはり芸術が担うところが大なのではないか?と
私は常々考えている。
その考えからすれば、、彼のこのテーマ性とコンセ
プトは衝撃であった。。。。。。。。
日本が今後日本として世界に伍していくとき
それほど選択の余地はない。
おそらく世界全体の総体的感性から日本を見れば
その優位性とは、間違いなく科学技術に特化する
ことは明白である。
これはある意味のナショナリティーとなり得る
近未来の日本の国家観でもある。
そうなれば・・
確かにアニメという日本芸術の歴史をトランスレート
した超平滑(スーパーフラット)は引き続き芸術的
ナショナリティーの要素を成すであろうが、それよりも
この科学技術を背景としたコンセプトはもっと大きな
ものになるかも?と感じたのでした。
当然、過去を見てもこのようなものが全く無かったか?
と言えば、そんな事はないだろう・・・
しかし、これの大きな違いは、科学技術の世界と芸術
の世界が”パラレル”ではないという点だ・・・
芸術的感性で現代科学を翻訳したり、普遍的人間性を
詩情化している訳ではない・・
科学と芸術が同次元で合体して
可視化効果を作り出している。。
協力: 太陽誘電株式会社(リチウムイオンキャパシ
タ提供)、ビフレステック株式会社(回路技術提供)、
京セミ株式会社(球状太陽電池提供)、という企業
が深く関わりをもって展覧の形をなしている。
メセナ的な表面の関わりではないそして、それは前
時代的なパトロニズムでないことは展覧コンセプト
を見れば明白である・・・・
なんというのだろうか・・・
少し打ちのめされた、、という感覚と
モーゼの出エジプトのような感覚と・・
間違いなく
見えたものがありました。。
事前に田村さんには細かい注文を出し
高松まで同行してもらい設営もお願いしたのですが、
実は今回の同行は、その展開設営だけが目的ではなく
もう一つ田村さんとの計画?がありました。
以前より”直島”に一緒に行きましょう!と約束して
おり、今回ようやく実現させることができたのでした。
直島行き!
それは今後の田村さんの制作活動には必ず大きな刺激に
なると確信するところであり、ひいては私どもの今後の
展開にも大きなメリットがある事であり、是非とも一緒に
行こうとかなり以前から話し合っていたのでした。。
私も、一年ぶりで、少し確認したい事もあり。。。。。
と、、言うわけで今回は”直島行き”レポートのような
始まりなのですが、、
それは次回・・・
今回は、直島行きの前日に田村さんとご一緒した
香川県丸亀市の丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(MIMOCA)
へ行ったレポートです。


実はこの美術館も田村さんには見ていただきたかったの
です。

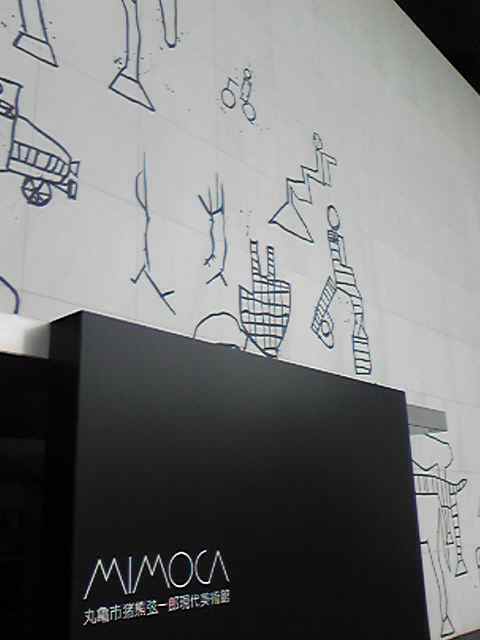
私は、このブログで再々香川県の特殊性を書いてきたと
思うのですが・・・(そうでもないかな??)
ひょんな事で行き出して丸9年、今年は10年目になる
のですが、初期、この四国北東部の、、このエリアは何故
これほど現代美術というのか先進的なアートに敏感なのか?
不思議でしょうがなく、それは今も続く感覚で明確な答え
といえるものはないのですが、確実なる一つがあるとする
ならば、この猪熊弦一郎というアーティストがこの地域の
出身で、斬新なアートの先達であったこととの関係が深い
事だけは確信しうる事実かなと思う。


他人に言わせると、何故君は高松ばかり行くの?となるが
私としては、今のこの仕事、もし仮にこの世界、特に先進
的な芸術を模索する世界に身を置いていて、なぜ行かない
の?と逆に聞き返したくなる、、のである。
という事でその話はまた後日じっくりするとして、、
先ず今回の丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(MIMOCA)訪問に
さいして一つ伝えたいのは、、
じっくり良く考えていただきたいのですが、昨今様々な
事業仕訳等の行政の無駄をスリム化する世相にあって決し
て人口が多い街でもなければ、到底都会に比べ資金力が
あるとは思えない、一地方都市、それも小さな街が、市営
でこのような難解な現代美術館を硬派にも運営し続けてい
るというのは驚愕と同時に称賛に値することを認識してい
ただきたい。東京名古屋大阪広島福岡であればさほど不思
議はない、まぁ少し譲って金沢・茨城・・・
※京都などはダラシナイ代表選手だ・・
しかし、、、、
丸亀市でこの内容!これは改めてスゴイと言わざるを得ない。
市営ということは議会で決をとり税金で運営している訳で、
市民納得の上という事であり・・


現代美術=訳の分からん?などという感性では無いのだ!

この一事を考えてもこのエリアの特異な感性に興味を持ち
続けるのはまったく不思議はないだろう。。
--------------------------------------------------
田村さんともこの事を様々話をし大いに盛り上がりました。
さて美術館ですが、さすが田村さんはもともとインテリア
や商業施設のデザイナーだけあり、我々とは見方が違い、
先ず美術館の建築から細かく見ておられました。。
こういう方と一緒に行くというのは、こういった部分で
私としても実に刺激的であり、今まで知らなかったこと
を実地で教えてもらい大いに勉強になるのでした・・
肝心の展覧ですが、残念ながらほぼ常設展に近く、猪熊
作品の色をテーマとした展覧でしたが、それはそれなりに
面白く時間をかけて二人展観いたしました・・・・・
が、、、、、、、、
実は残念どころか!!!!!
すごいモノに出会いました・・・
まったく知らなかったのですが、、
美術館の正面玄関に猪熊展以外にもう一つ??
Focus3 高嶺 格:スーパーキャパシターズ
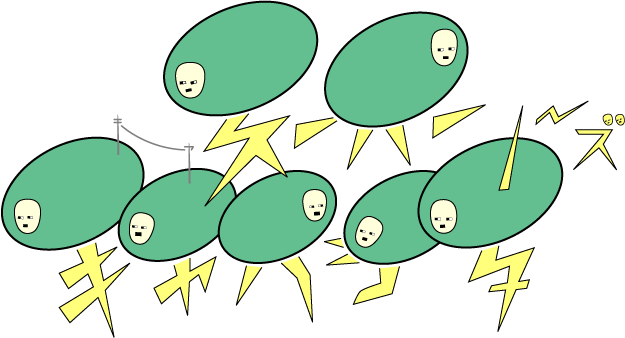
なんじゃ?こりゃ?
と、あまり期待せず覗いたのですが・・・
電撃が身体を突き抜けました。。。。
ここで美術館のステートメントを転載いたしますが
-----------------------------------------------------
以下、Focus3 高嶺 格:スーパーキャパシターズ
丸亀市猪熊弦一郎現代美術館ステートメント。
現代に鋭い視線を向けるアーティストの珠玉の作品に焦点を
絞って紹介する個展シリーズ“Focus”の第3弾です。
今回は、社会の抱える様々な矛盾や軋轢を、自分自身の問題
としてとらえ、正面から向き合って考えることから作品を生
み出し続けているアーティスト、高嶺格(たかみねただす/
1968年鹿児島県生まれ)の作品「スーパーキャパシターズ」
をご紹介します。
「スーパーキャパシタ」とは、市販されている蓄電装置の名前
です。乾電池やバッテリーに比べ、安価で安心な素材で製造で
きる上、劣化しにくく長期にわたって繰り返し使用できるとい
った画期的な性質を備えています。代替エネルギーへの取り組
みが急がれる昨今、このキャパシタや太陽電池をはじめとして、
持続可能性を視野に入れた新技術の研究開発が盛んに行われて
いますが、一方で、このような技術や考え方が確立されたとし
ても、それが市場の中で既存の技術と入れ替わるまでには、か
なり時間がかかってしまうという問題があります。いいはずの
ものがなかなか普及できない、高嶺はこのジレンマに注目し、
美術の力をもって普及の加速化を試みます。すなわち、これら
新技術にイメージを与え、ブランド化を仕掛けることで、一刻
も早い低価格化を目論むのです。2008年スタートした(*)
高嶺の「スーパーキャパシタ」キャンペーンは、その後の技術
革新も反映し、新たなアイテムをつけ加えて、2010年さらなる
拡張を図ります。
※“Focus”について
MIMOCA(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館)の2階展示室フロ
アの一室を使った展覧会シリーズで、MIMOCAがピックアッ
プした国内外で活躍するアーティストの珠玉の作品をご紹介する
ものです。
本展は、2006年開催の「スティーヴ・マックィーン[Caresses]」、
2008年開催の「エイヤ=リーサ・アハティラ展」につづく、第3
回展となります。
--------------------------------------------------------
展覧自体の風景は
所謂、無機質なミニマルアート的ではあるのですが・・・・
私が電撃を受けたというのは、このコンセプトです。
今後の現代美術と呼ばれるものが向かう、特に日本の
現代美術が突き抜けていく一つの大きな方向性が漠然と
ではありますが、この作家の示す方向ではないか?と
感じたのでした・・
このコンセプトは必ず大きな芸術的概念化を遂げ
世界に向けた大きな潮流となる。
特に
いいはずのものがなかなか普及できない、高嶺はこの
ジレンマに注目し、美術の力をもって普及の加速化を
試みます。
という部分・・・
今世界的に様々な分野が閉塞感に苛まれている現代、
全てにおいて循環に破綻が差し迫っている世紀
・・・苦しい逆境の中で、、、
乗り越えなくてはならない現実
その為の人間哲学、科学技術、、、、等々
我々は新たな人間生活を社会を循環させていく為に
新たな論理を生み出さなくてはならない。
それは、”排除”の論理ではなく”共生”の論理で
あり、その根幹となる人間感性の刺激は、、
やはり芸術が担うところが大なのではないか?と
私は常々考えている。
その考えからすれば、、彼のこのテーマ性とコンセ
プトは衝撃であった。。。。。。。。
日本が今後日本として世界に伍していくとき
それほど選択の余地はない。
おそらく世界全体の総体的感性から日本を見れば
その優位性とは、間違いなく科学技術に特化する
ことは明白である。
これはある意味のナショナリティーとなり得る
近未来の日本の国家観でもある。
そうなれば・・
確かにアニメという日本芸術の歴史をトランスレート
した超平滑(スーパーフラット)は引き続き芸術的
ナショナリティーの要素を成すであろうが、それよりも
この科学技術を背景としたコンセプトはもっと大きな
ものになるかも?と感じたのでした。
当然、過去を見てもこのようなものが全く無かったか?
と言えば、そんな事はないだろう・・・
しかし、これの大きな違いは、科学技術の世界と芸術
の世界が”パラレル”ではないという点だ・・・
芸術的感性で現代科学を翻訳したり、普遍的人間性を
詩情化している訳ではない・・
科学と芸術が同次元で合体して
可視化効果を作り出している。。
協力: 太陽誘電株式会社(リチウムイオンキャパシ
タ提供)、ビフレステック株式会社(回路技術提供)、
京セミ株式会社(球状太陽電池提供)、という企業
が深く関わりをもって展覧の形をなしている。
メセナ的な表面の関わりではないそして、それは前
時代的なパトロニズムでないことは展覧コンセプト
を見れば明白である・・・・
なんというのだろうか・・・
少し打ちのめされた、、という感覚と
モーゼの出エジプトのような感覚と・・
間違いなく
見えたものがありました。。


