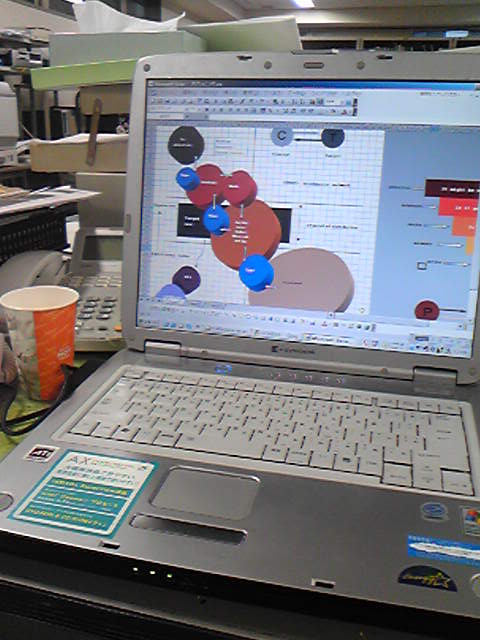February 5,2010
上海報告のつづき、、ですが・・・
と始めたいところですが、、
なんと気づくと一週間も開いてしまった。。
この間、、何と言うことなくバタバタと動き周り
多少の体調不良にも悩まされながら、、、
と言うことで、実は、この報告を終わる前に
上海BIZアクションプランの検討会議が既に
行われ、KFLのFさんKさんともおおよその
方向性を確認し如何に先ず春のアートシーズ
ンに突入していくか?などというような機運
が盛り上がっている昨今、、、
私のブログでの”グニュグニュ”とした報告を・・・・
現実が猛スピードで追い越していくような
状態で・・・・・
。。。。。。。。。。。。。。
もうちょっと真剣に取り組まねばと改めて
思ったしだいです・・
と言うことで、、牛のよだれ、アホの生涯
”年寄りの小便”・・・・
何というのか、、年いけば、、中年ごろからか?・・
”コクはあるけど、、切れはない”
と、、少しソレましがた・・
の、ように眠たいくらい感覚が開いてしまいまし
たが、最後の報告を・・・
上海出張、最終日はM50に訪問しました。






実は私数年前一度訪問したことがあるので
今回は2回目になります。
現状は知らないのですが、数年前、この
M50という工場跡地を使用したアートエリア
は上海の現代アートを取り扱う最先端のスポット
という触れ込みで、海外からも多数の来訪者を
招き入れ活況を呈していました。
その評判を耳にした私も、大した目的もなく伺った
のでした。その時の印象とは、作品等のレベルや洗練
された感覚の問題は別にして、息吹というのか勢いに
は目を見張るものがあり、日本でこの手のスポットで
感じるものとは比べモノにならない程圧倒されたのを
覚えています・・・


その時とくらべての変化は、中身は良くわからないが、
建物の外観等、雰囲気そのものは数年前とさほど変わ
ることはありませんでしたが、、、、
しかし、なにか?・・・


問題は中身なのですが、、、、
今回この場所を伺った理由は、先のブログでも
紹介させてもらいました、上海のオークション
ハウスディレクターからの推薦で、ある有能な
女性ギャラリストを訪ねにいったのでした。


日本への留学経験やその他、外国にての経験が
豊富なその方は、実に丁寧に上海のアートマー
ケットの実情を”流暢な日本語”を駆使し我々
に教えてくれたのでした。。





日本人か?と見紛うようなその流暢な言葉は、
ほとんど日本で話をしているのと変わらない
レベルで、実際彼女も日本とのビジネスを
模索・進行させている途上であり、お互い
情報を交換する上ではメリットの高い関係で
あることをいち早く察知できたのでした。

これは大きな収穫ではありました。
その彼女が言うには、、
現在、M50内には約100軒近くギャラリー
が存在するようで、その家賃も聞くと驚くほど
高いものでした。
(場所代が高い、賃料が高い=ロケーションの価値が高い
それだけでビジネスとしては成立する。。所謂、レンタ
ルスペースである。)
まぁそれら現象面的なここ数年の変化
なのですが・・
問題は、それよりもなによりも
実際のマーケットは、M50に限らず、全体が
未だ混沌としてる状況があり、整理されていな
いというのが実際の”プレイヤー達が素直に
感じる実情のようでした。。
改革開放、アートバブル、リーマンショック、、
これらを経て、それぞれの時代に特異な動きが
マーケットに顕在化したのであるが、それは
あたかも雨後の竹の子のようであり、それぞれ
がバラバラの事情と背景を元に頭角を現した、、
どちらかと言うと、全体的な欲求からの必然性
ではなく、散発的に個々の欲求に沿って現出し
たというのが実情であった。。。
これを、その都度メディアが体系化された中
でのポジションを把握し報道すると言うこと
行った訳ではなく、ただ流動する状況を垂れ
流しているのが実際でありました。
その実情をキャッチし脆弱な考察を繰り返して
きたのが日本のアート界を中心としたメディア
であり、春秋のフェアに参加してきたギャラリー
たちであったように私は感じました。
故に本質的な全体を俯瞰したようなマーケット
情報は皆無と言ってよい。
情報それぞれに正確不正確はあります、しかし
実情から過去の情報を考察した場合、大まかに
感じるのは枝葉末節的な把握、これが大きい
かな?と感じたのでした。
全体を俯瞰した状況及び全体像の構築が今はない、
というのがこの国の現状で間違いないというのと
同時に、実は今そこに向かっているのかも?とい
うのが私の感じた実情でした。
それぞれの国がそれぞれの歴史的な背景を元に
アート界のヒエラルキーが構築され、それを元に
価値というものが形成されているはずなのですが
中国においては、この急激な発展過程が、実は
様々なものを飛び越えて成立していいき、後付
でその空白となった場所を埋める、そのような
感じがあるのではないか?
例えば良く言われることではあるのですが、
日本の電話というものの成立過程を考えれば
もともと”ガリガリ・・への何番!”などと
いう交換手を通じての通信だったのが、黒い
固定電話へ変化し、そこからプッシュ回線
そしてご存じのような携帯電話という時代
の形成過程を経るのですが、これを下敷きに
中国を考えれば、失礼だが、電話がない時代
からいきなり携帯電話の通信時代へワープした
ようなもので、日本が経た文化的形成過程を
ほとんど飛び越えている・・というのが実情
として分かる。
実はこの事実は一事が万事のように私は感じる
のである。アートの世界も同様であり、ギャラリー
の存在やアートを買うという世界が形成された仮
定の多くが中国ではかなりショートカットされて
いると考えるのが実は自然な現状把握なのではな
いか?と思うのと同時に。、、、、
そういう意味で、、、
シュートカットしてたどり着いている現状とは
欧米の先進的マーケット感覚なのではないか?と
考えて違和感はない。
間違いなく、日本が形成してきた情緒的マーケ
ット感覚で無いことだけは確かではないだろうか??
さて、このような状況を感覚的に掴んだ我々は
如何にすべきなのか?
実は形成過程上の問題を別にすれば、表面的な
アートビジネスのマインドは同水準、sの上の
強みは資金豊富、このような現状で、これから
国内で全体的な動きが起ころうとしている状況
で、わざわざなんのために日本からものを買う
必要があるのか?仮にそういった事に興味を持
つとするならば、それは一体どんな根拠が存在
するのか?
日本ブランド?アニメイズム?ムラカミ、ナラ
クサマ・・・
ここに何とも言えない蜃気楼的な夢想が開くの
だと思う・・・
しかし、それは日本でも一部の世界を代表しうる
銘柄の話であり、我々にはそういったものは皆無
である。
もし仮に、彼らは全体像を知らない、、、
十把一絡げにて日本を把握しているという、、、
経済成長との関係で大雑把な価値観のギャップ
が生まれているなどというような感覚を不用意に
もてば、それは間違いなく火傷の元のようにも
感じた。
そんなに甘くはない・・・
彼らは”もっともっとシビアー”でもある・・
一時、香港あたりでこのような感覚的な蜃気楼が
多発していたようであるが・・・
それもやはり今となっては蜃気楼でしかなかった。。
我々の作家
それは申し訳ない言い方になるが、
無名でしかない。
日本国内でも決して客観的評価が高い訳では
ない・・・
それは誠に厳しい言い方ではあるが
”価値がない”という事にも相応する。
この現状、これが我々の現実なのではないか?
だからただ単純にアートフェアに出かけても
根拠ある商売が成り立たない、、出会い頭や
偶然はあっても・・恒常性もなければ成長も
ない・・・
可能性があると言っても、そんな情緒的な、そして
客観的な判断材料が乏しいものに一々付き合う
人間がいるとは思えない。ましてや、可能性
ということで考えれば、それは中国国内で完結さ
せてもなんら問題ない事柄であり、実際にはその
ほうが、現地の人間にとっては、、、
夢がある!
わざわざ海の向こうの”どこの馬の骨ともわからない”
人間にそんな可能性を見いだす!などという夢絵空事
のようなモノに貴重な時間と資力を提示する奇特な
人間がいるとは思えないのである。。。。
この現状で
どこにビジネスの”ドッキングポイント”があるのか?
私は正直、色んな可能性を秘めた地であることに
異論はない。当然、混沌としている状況にはチャンスが
豊富にあることは間違いないだろう。しかしそれを
果たして外国からやってきてそう簡単に掴めるのだろう
か?と思うのも自然な感情としてもっている。
根本的に、じゃ、、そんな夢を見ずに日本でコツコツ
やればええやないか?となるのも自然だと感じるし、
日本でできないものが、、なんで上海でできるのか?
という批判も正確だと認識する。
わざわざなんで上海なのか?
この基本は日本でやれない(これは諦めてではなく、、、)
ことを上海でやるから行く意味が生まれるのであって
それが一体何なのか?それを考えなければ、
当然、何をしにきた?何のため?という事に
しかならないのと同時に、それが明確さを
保てないのであるならば行く意味がない。
そしてもっとも大事なのは、上海側にそんなものを
持ち込み、果たして受けるとる側が求めるものにな
るのか否か?
需要が生まれなければ本当に行く意味は生まれない。
そのためには、漠然とした突貫では粉砕することは
目に見えている。この数日の出張で感じた感覚で
もうすでに結論はでた。
やはり戦術が要る。そして熟慮がいる。
冷静になれば自らの存在、客観的な姿が浮かび
上がる。その姿とは、、
我々は間違いなく
小たる存在である。
中国上海は大なる存在である。
古今、小が大なる相手を倒す戦術はそれほど
多く無いことは歴史が実証している。。
戦術の選択はさほどない。
ある意味、錐をもむが如く一点に集中し
力の散逸を防ぎ突き抜けることしかない
ように思うのである・・・
その為に
私が思うのは
陽動+挟撃
陽動+挟撃+ゲリラ
陽動+挟撃+ゲリラ+外交
陽動+挟撃+ゲリラ+外交+遊撃的支援
+支援
陽動+挟撃+ゲリラ+外交+遊撃的支援
+支援+政治的介添え
陽動+挟撃+ゲリラ+外交+遊撃的支援
+支援+政治的介添え+外交勝利
このような法則しかないように感じた。
これが如何に具体化していくか、いや
させるかは、また後日報告させてください。。
------------------------
さて、最後になりますが。。
先のアートフェアで
いつも応援して下さっている敬慕の念の尽きない大事な
お客様から言われた一言
”貴方はなにをもって成功と呼ぶの!”
これは、ずっと続く課題というよりも、先ず根本的な考
えをブレなく強固に持ち、それをチャレンジしなくては
いけないという戒めでもありました。
実は
出張中にもメールを頂きました。
”心と心で会話しなさい!”
これを受けたとき、ハッと目が覚めました。
これが今回の報告のもとになった感覚です。
この言葉だけから受けるのは、自分をさらけ出し
腹を割って話して・・・というようなモノを感じ
ないでもないが、、、
しかし、ここで冷静に考えれば、、、
本当に”心と心で会話”するには、同じレベルに
達していなければ真の心の会話は成立しない?の
じゃないの?と感じたのでした。
我々はビジネスで向き合う訳である、そのとき
どちらか一方になにかの依頼心や依存度が偏重して
いて本当に心の会話などになるのであろうか?
それはボランティア的慈善精神でしかなく、お互い
のメリットを正確に話し合うにつけては、やはり
お互いが認めあう存在にならなくては話にならない。
逆もある、、騙されるということである。。
そう考えれば、とても今の現状ではお互い相互の
メリット創出などというレベルではない。
しかし、足りない自分というものは十分にこの
言葉、本当の意味の”心と心”から理解できた、
どうすべきか?も把握できる。
まずは心と心の会話に必要な自分、とCOMBINEを
追求しなくてはいけない。
それは今後の上海BIZの骨格となる
重大事であることに気づかされました。。。。
------------------------
おまけ!
COMBINE+KFL M50視察風景・・・
と始めたいところですが、、
なんと気づくと一週間も開いてしまった。。
この間、、何と言うことなくバタバタと動き周り
多少の体調不良にも悩まされながら、、、
と言うことで、実は、この報告を終わる前に
上海BIZアクションプランの検討会議が既に
行われ、KFLのFさんKさんともおおよその
方向性を確認し如何に先ず春のアートシーズ
ンに突入していくか?などというような機運
が盛り上がっている昨今、、、
私のブログでの”グニュグニュ”とした報告を・・・・
現実が猛スピードで追い越していくような
状態で・・・・・
。。。。。。。。。。。。。。
もうちょっと真剣に取り組まねばと改めて
思ったしだいです・・
と言うことで、、牛のよだれ、アホの生涯
”年寄りの小便”・・・・
何というのか、、年いけば、、中年ごろからか?・・
”コクはあるけど、、切れはない”
と、、少しソレましがた・・
の、ように眠たいくらい感覚が開いてしまいまし
たが、最後の報告を・・・
上海出張、最終日はM50に訪問しました。






実は私数年前一度訪問したことがあるので
今回は2回目になります。
現状は知らないのですが、数年前、この
M50という工場跡地を使用したアートエリア
は上海の現代アートを取り扱う最先端のスポット
という触れ込みで、海外からも多数の来訪者を
招き入れ活況を呈していました。
その評判を耳にした私も、大した目的もなく伺った
のでした。その時の印象とは、作品等のレベルや洗練
された感覚の問題は別にして、息吹というのか勢いに
は目を見張るものがあり、日本でこの手のスポットで
感じるものとは比べモノにならない程圧倒されたのを
覚えています・・・


その時とくらべての変化は、中身は良くわからないが、
建物の外観等、雰囲気そのものは数年前とさほど変わ
ることはありませんでしたが、、、、
しかし、なにか?・・・


問題は中身なのですが、、、、
今回この場所を伺った理由は、先のブログでも
紹介させてもらいました、上海のオークション
ハウスディレクターからの推薦で、ある有能な
女性ギャラリストを訪ねにいったのでした。


日本への留学経験やその他、外国にての経験が
豊富なその方は、実に丁寧に上海のアートマー
ケットの実情を”流暢な日本語”を駆使し我々
に教えてくれたのでした。。





日本人か?と見紛うようなその流暢な言葉は、
ほとんど日本で話をしているのと変わらない
レベルで、実際彼女も日本とのビジネスを
模索・進行させている途上であり、お互い
情報を交換する上ではメリットの高い関係で
あることをいち早く察知できたのでした。

これは大きな収穫ではありました。
その彼女が言うには、、
現在、M50内には約100軒近くギャラリー
が存在するようで、その家賃も聞くと驚くほど
高いものでした。
(場所代が高い、賃料が高い=ロケーションの価値が高い
それだけでビジネスとしては成立する。。所謂、レンタ
ルスペースである。)
まぁそれら現象面的なここ数年の変化
なのですが・・
問題は、それよりもなによりも
実際のマーケットは、M50に限らず、全体が
未だ混沌としてる状況があり、整理されていな
いというのが実際の”プレイヤー達が素直に
感じる実情のようでした。。
改革開放、アートバブル、リーマンショック、、
これらを経て、それぞれの時代に特異な動きが
マーケットに顕在化したのであるが、それは
あたかも雨後の竹の子のようであり、それぞれ
がバラバラの事情と背景を元に頭角を現した、、
どちらかと言うと、全体的な欲求からの必然性
ではなく、散発的に個々の欲求に沿って現出し
たというのが実情であった。。。
これを、その都度メディアが体系化された中
でのポジションを把握し報道すると言うこと
行った訳ではなく、ただ流動する状況を垂れ
流しているのが実際でありました。
その実情をキャッチし脆弱な考察を繰り返して
きたのが日本のアート界を中心としたメディア
であり、春秋のフェアに参加してきたギャラリー
たちであったように私は感じました。
故に本質的な全体を俯瞰したようなマーケット
情報は皆無と言ってよい。
情報それぞれに正確不正確はあります、しかし
実情から過去の情報を考察した場合、大まかに
感じるのは枝葉末節的な把握、これが大きい
かな?と感じたのでした。
全体を俯瞰した状況及び全体像の構築が今はない、
というのがこの国の現状で間違いないというのと
同時に、実は今そこに向かっているのかも?とい
うのが私の感じた実情でした。
それぞれの国がそれぞれの歴史的な背景を元に
アート界のヒエラルキーが構築され、それを元に
価値というものが形成されているはずなのですが
中国においては、この急激な発展過程が、実は
様々なものを飛び越えて成立していいき、後付
でその空白となった場所を埋める、そのような
感じがあるのではないか?
例えば良く言われることではあるのですが、
日本の電話というものの成立過程を考えれば
もともと”ガリガリ・・への何番!”などと
いう交換手を通じての通信だったのが、黒い
固定電話へ変化し、そこからプッシュ回線
そしてご存じのような携帯電話という時代
の形成過程を経るのですが、これを下敷きに
中国を考えれば、失礼だが、電話がない時代
からいきなり携帯電話の通信時代へワープした
ようなもので、日本が経た文化的形成過程を
ほとんど飛び越えている・・というのが実情
として分かる。
実はこの事実は一事が万事のように私は感じる
のである。アートの世界も同様であり、ギャラリー
の存在やアートを買うという世界が形成された仮
定の多くが中国ではかなりショートカットされて
いると考えるのが実は自然な現状把握なのではな
いか?と思うのと同時に。、、、、
そういう意味で、、、
シュートカットしてたどり着いている現状とは
欧米の先進的マーケット感覚なのではないか?と
考えて違和感はない。
間違いなく、日本が形成してきた情緒的マーケ
ット感覚で無いことだけは確かではないだろうか??
さて、このような状況を感覚的に掴んだ我々は
如何にすべきなのか?
実は形成過程上の問題を別にすれば、表面的な
アートビジネスのマインドは同水準、sの上の
強みは資金豊富、このような現状で、これから
国内で全体的な動きが起ころうとしている状況
で、わざわざなんのために日本からものを買う
必要があるのか?仮にそういった事に興味を持
つとするならば、それは一体どんな根拠が存在
するのか?
日本ブランド?アニメイズム?ムラカミ、ナラ
クサマ・・・
ここに何とも言えない蜃気楼的な夢想が開くの
だと思う・・・
しかし、それは日本でも一部の世界を代表しうる
銘柄の話であり、我々にはそういったものは皆無
である。
もし仮に、彼らは全体像を知らない、、、
十把一絡げにて日本を把握しているという、、、
経済成長との関係で大雑把な価値観のギャップ
が生まれているなどというような感覚を不用意に
もてば、それは間違いなく火傷の元のようにも
感じた。
そんなに甘くはない・・・
彼らは”もっともっとシビアー”でもある・・
一時、香港あたりでこのような感覚的な蜃気楼が
多発していたようであるが・・・
それもやはり今となっては蜃気楼でしかなかった。。
我々の作家
それは申し訳ない言い方になるが、
無名でしかない。
日本国内でも決して客観的評価が高い訳では
ない・・・
それは誠に厳しい言い方ではあるが
”価値がない”という事にも相応する。
この現状、これが我々の現実なのではないか?
だからただ単純にアートフェアに出かけても
根拠ある商売が成り立たない、、出会い頭や
偶然はあっても・・恒常性もなければ成長も
ない・・・
可能性があると言っても、そんな情緒的な、そして
客観的な判断材料が乏しいものに一々付き合う
人間がいるとは思えない。ましてや、可能性
ということで考えれば、それは中国国内で完結さ
せてもなんら問題ない事柄であり、実際にはその
ほうが、現地の人間にとっては、、、
夢がある!
わざわざ海の向こうの”どこの馬の骨ともわからない”
人間にそんな可能性を見いだす!などという夢絵空事
のようなモノに貴重な時間と資力を提示する奇特な
人間がいるとは思えないのである。。。。
この現状で
どこにビジネスの”ドッキングポイント”があるのか?
私は正直、色んな可能性を秘めた地であることに
異論はない。当然、混沌としている状況にはチャンスが
豊富にあることは間違いないだろう。しかしそれを
果たして外国からやってきてそう簡単に掴めるのだろう
か?と思うのも自然な感情としてもっている。
根本的に、じゃ、、そんな夢を見ずに日本でコツコツ
やればええやないか?となるのも自然だと感じるし、
日本でできないものが、、なんで上海でできるのか?
という批判も正確だと認識する。
わざわざなんで上海なのか?
この基本は日本でやれない(これは諦めてではなく、、、)
ことを上海でやるから行く意味が生まれるのであって
それが一体何なのか?それを考えなければ、
当然、何をしにきた?何のため?という事に
しかならないのと同時に、それが明確さを
保てないのであるならば行く意味がない。
そしてもっとも大事なのは、上海側にそんなものを
持ち込み、果たして受けるとる側が求めるものにな
るのか否か?
需要が生まれなければ本当に行く意味は生まれない。
そのためには、漠然とした突貫では粉砕することは
目に見えている。この数日の出張で感じた感覚で
もうすでに結論はでた。
やはり戦術が要る。そして熟慮がいる。
冷静になれば自らの存在、客観的な姿が浮かび
上がる。その姿とは、、
我々は間違いなく
小たる存在である。
中国上海は大なる存在である。
古今、小が大なる相手を倒す戦術はそれほど
多く無いことは歴史が実証している。。
戦術の選択はさほどない。
ある意味、錐をもむが如く一点に集中し
力の散逸を防ぎ突き抜けることしかない
ように思うのである・・・
その為に
私が思うのは
陽動+挟撃
陽動+挟撃+ゲリラ
陽動+挟撃+ゲリラ+外交
陽動+挟撃+ゲリラ+外交+遊撃的支援
+支援
陽動+挟撃+ゲリラ+外交+遊撃的支援
+支援+政治的介添え
陽動+挟撃+ゲリラ+外交+遊撃的支援
+支援+政治的介添え+外交勝利
このような法則しかないように感じた。
これが如何に具体化していくか、いや
させるかは、また後日報告させてください。。
------------------------
さて、最後になりますが。。
先のアートフェアで
いつも応援して下さっている敬慕の念の尽きない大事な
お客様から言われた一言
”貴方はなにをもって成功と呼ぶの!”
これは、ずっと続く課題というよりも、先ず根本的な考
えをブレなく強固に持ち、それをチャレンジしなくては
いけないという戒めでもありました。
実は
出張中にもメールを頂きました。
”心と心で会話しなさい!”
これを受けたとき、ハッと目が覚めました。
これが今回の報告のもとになった感覚です。
この言葉だけから受けるのは、自分をさらけ出し
腹を割って話して・・・というようなモノを感じ
ないでもないが、、、
しかし、ここで冷静に考えれば、、、
本当に”心と心で会話”するには、同じレベルに
達していなければ真の心の会話は成立しない?の
じゃないの?と感じたのでした。
我々はビジネスで向き合う訳である、そのとき
どちらか一方になにかの依頼心や依存度が偏重して
いて本当に心の会話などになるのであろうか?
それはボランティア的慈善精神でしかなく、お互い
のメリットを正確に話し合うにつけては、やはり
お互いが認めあう存在にならなくては話にならない。
逆もある、、騙されるということである。。
そう考えれば、とても今の現状ではお互い相互の
メリット創出などというレベルではない。
しかし、足りない自分というものは十分にこの
言葉、本当の意味の”心と心”から理解できた、
どうすべきか?も把握できる。
まずは心と心の会話に必要な自分、とCOMBINEを
追求しなくてはいけない。
それは今後の上海BIZの骨格となる
重大事であることに気づかされました。。。。
------------------------
おまけ!
COMBINE+KFL M50視察風景・・・