February 15,2010
実は、、
Kappaちゃんは去年から挑戦を続けている。
昨年のBAMIgalleryでの個展が終了したと
き、少し今後のことを話した。
昨年の個展そのものは新作かきおろしと
いう事ではなく、それまで描きためた作品
をテーマ性(厳密には絵柄を中心として
選別した構成)を持って編集し直し展覧し
たのだが、私は、この展覧でなんとなく見
えたものがあった。
散漫。
これが実は私の率直な感想であった。
確かに彼女がステートメントで書くように
「私は、人の中にある姿を描きたいと思って
います。年齢や性別などに関係のない、人
の、その奥にある姿を描きたいです。」
と言うようにそれに沿った内容にて作画さ
れているのだが、どうもそれは言葉の説明を
介さないと伝わらないような気がしたので
ある。
事実、彼女は全ての作品に散文詩的なものを
必ず付加していた。
これを同時に見ると、ある種の共有感は生ま
れる。
実はこれが私は不満であった。
そんなものが要るのだろうか?絵に?
絵は言葉ではない。
、しかし某かの感情的、伝達を発する。
確かにそこに描かれた日常的なモチーフ
がアイコンとなり言語化する事もあるが、
力のある絵は、ドンと何か分からないモ
ノが、突如心の内側に飛び込んでくる・・
これは、ある種の”暴力”に近いものだ
と私は思うのである。傍若無人にも人の
心にズカズカと入り込んできて、勝手に
人の心をザワつかせ、何故にという答えを
渡すこともなく居続ける・・・・
とんでもない粘着力。。
いいなぁ~・・・などという感情は
ある意味、”疵”つけられているのだ。。。
もっと言えば、
誰もが内在していて、かすかな記憶にしかな
い、もしくはそのようにしている傷口に
”塩を塗りこまれている”ようなものだ・・
この異様な能力、、、
傷つけるもしくは、傷口の塩を塗りこむ、、
絵そのものが人格を持ち、見る人間の心の
防御を突破し、人の心の疵に突き刺さる・・
絵画、
日本人で一番力があったのは鴨居玲だと
私は思うのだが、、、
KAPPAちゃん、彼女が書くステートメント、
これはシンプルで且つ良いと私は思った、
しかし如何せんそこに絵が到達するには今
少しの取り組みが必要じゃないか?と、、
このようなモノが見え隠れしたのが昨年の
個展だったのである。
私は僅かな助言をした。
大きな絵を描いてみない?
ただ単に大きな作品を描くのではなく、今回
の個展で並べた絵を、一枚に凝縮するような
絵を描いてみては?
あらゆる角度で”人の中にある姿”を今は
描いているけど、それを一枚で表すのではな
く”現して”みてくれない?
ある意味、”不気味な一人の人間を”・・・
という宿題を課したのであった。
何となく分かっていた。それまでの絵は
詩作に近かった、しかし私が提示したもの
は”小説”である。
小説は一つの事を伝えるために、場合によ
っては何万語も費やす・・・
竜馬がゆく
司馬遼太郎は竜馬以外を書いた訳ではない
あくまで竜馬である・・・・
結果はある一つの事を伝達することでしかな
い。
しかし、読んだ人間が受けたのは
竜馬の時系列の活躍か?
この作業を一度して欲しかったのである。
決して詩作が悪いわけではない。
瞬発的に出来るモノと、かなりの制御と材料
を必要とする小説では違うような気がする
というのは大きな間違いで、実は逆転して
考えれば、小説を凝縮したのが詩作でもある。
その瞬発力の根幹にはやはり小説的材料の
凝縮が必要となる・・・
この相互の作業を知らずして詩作に励んでも・・
先に大きくなるような感じを受けないのと同時に
小説的なものも知らないまま終わりそうな気がし
たのである・・
そして数ヶ月後、あるコンペに入選した。
その作品は確かにそれまでのモノとは見違える
ようなすばらしい出来だった。

その直後、私は次の宿題を彼女に課した。
小さいモノを一つのテーマで連作で描いてく
れない?
これは単純に先に書いた物の分解作業に近いの
だが、テーマという茫漠としたものに、一点集
中で向かう、そうすることにより、実は一点一
点があまり意味のないものと化す。何が残るか、
テーマがより浮かび上がるか否かという事であ
る。
一枚の絵を描くのに、箱に収納する一枚一枚の
絵という材料、その箱から傷つけず取り出して
いく一枚の絵・・
この答えが、実は現在展覧している
「不器用な色たち」の絵画の部分である。
一枚から取り出した一枚一枚の絵である・・
ここで想いもしない答えをKAPPAちゃんが出して
きた。実はこの「不器用な色たち」はF4で25枚
存在するのだが、これを全て足せば、出品の
基準サイズである100号となるのである。
物理的にKAPPAちゃんは分解していたのである。
この25枚の小品が出来てきた時に新たな宿題を
彼女に課した・・・
正直、これはどうかな?と少し悩んだのだが、、
それは?
立体を作らない?
というモノだった。
これを根拠なく言ったつもりはない。実はここ
までやって来た作業の中で、どうしても付け加
えたかったのだ。それは、、、
描いてきた人間を
取り出してみない?ということであった。
これを、私は見たかった。
これまでキャンバスに描いた様々な不思議な人間?
これを一度具体的に見てみたかった・・
どれほどのものか?
昨年KAPPAちゃんととある美術館へ同世代の知り合
いの女の子の展覧を見に行った。
そこにその女の子は立体を展示していた。
ここでKAPPAちゃんと話したのは
この美術館という環境を羨ましいと感じるか?
恐ろしいと感じるか?
私は正直に伝えたかったのは後者である。
本当の意味で万人に向き合う芸術作品とは
相当な強度を持っていなくては、簡単に
”へしゃげて”しまう。本当に自分にそこ
までの強度があるかないか?この判断が
実は大事な事なのだと思う。
なにも臆病になれというのではない。
しかしその女の子の作品を前に感じたのは
完璧ではないがそれなりの強度を保っていた。。
単純に”出てくる”ものがあった・・・
このときKAPPAちゃんと話し感じて欲しかっ
たのは・・
実存。
360°実存。
そんな絵をいつか描いて欲しいという
私の欲求であった・・・
そんな感覚を養って欲しかった。
だからその研究のために
立体を作って欲しかったのである。
立体に曖昧な着地点はない。ディティールの
粗雑さが全体を崩したり、なにかいい加減な
処理をしてお茶を濁しても、結果は許してく
れず全て崩壊する。
この構造を掴めば多分絵は大きく変わり、もっと
進化するんじゃないか?と考えたのでした。。
それが今回の立体作品です。
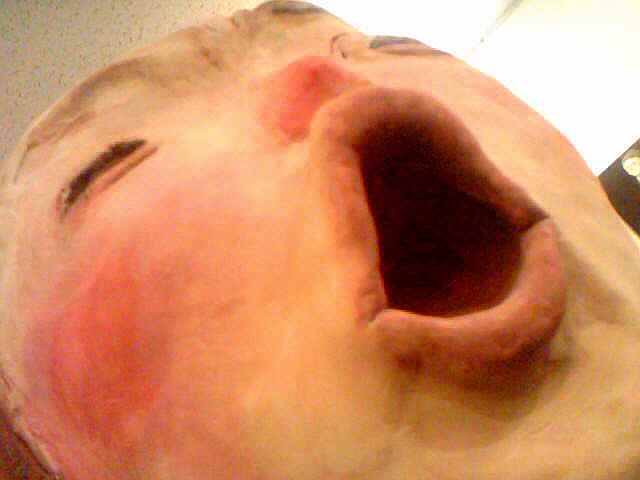
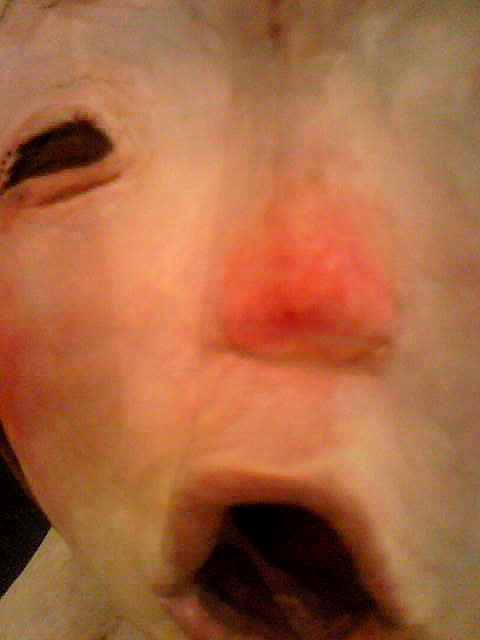
完璧ではけっして無い、強度も十分とは言えない
しかし、可能性がそこかしこと一杯顔を覗かして
いるのは間違いない。。

私は彼女が
今以上に飛躍する確信めいたものを今回掴んだ
ような気がした。
KAPPAちゃんと我々の挑戦はまだ始まったばっかり
だ!!
Kappaちゃんは去年から挑戦を続けている。
昨年のBAMIgalleryでの個展が終了したと
き、少し今後のことを話した。
昨年の個展そのものは新作かきおろしと
いう事ではなく、それまで描きためた作品
をテーマ性(厳密には絵柄を中心として
選別した構成)を持って編集し直し展覧し
たのだが、私は、この展覧でなんとなく見
えたものがあった。
散漫。
これが実は私の率直な感想であった。
確かに彼女がステートメントで書くように
「私は、人の中にある姿を描きたいと思って
います。年齢や性別などに関係のない、人
の、その奥にある姿を描きたいです。」
と言うようにそれに沿った内容にて作画さ
れているのだが、どうもそれは言葉の説明を
介さないと伝わらないような気がしたので
ある。
事実、彼女は全ての作品に散文詩的なものを
必ず付加していた。
これを同時に見ると、ある種の共有感は生ま
れる。
実はこれが私は不満であった。
そんなものが要るのだろうか?絵に?
絵は言葉ではない。
、しかし某かの感情的、伝達を発する。
確かにそこに描かれた日常的なモチーフ
がアイコンとなり言語化する事もあるが、
力のある絵は、ドンと何か分からないモ
ノが、突如心の内側に飛び込んでくる・・
これは、ある種の”暴力”に近いものだ
と私は思うのである。傍若無人にも人の
心にズカズカと入り込んできて、勝手に
人の心をザワつかせ、何故にという答えを
渡すこともなく居続ける・・・・
とんでもない粘着力。。
いいなぁ~・・・などという感情は
ある意味、”疵”つけられているのだ。。。
もっと言えば、
誰もが内在していて、かすかな記憶にしかな
い、もしくはそのようにしている傷口に
”塩を塗りこまれている”ようなものだ・・
この異様な能力、、、
傷つけるもしくは、傷口の塩を塗りこむ、、
絵そのものが人格を持ち、見る人間の心の
防御を突破し、人の心の疵に突き刺さる・・
絵画、
日本人で一番力があったのは鴨居玲だと
私は思うのだが、、、
KAPPAちゃん、彼女が書くステートメント、
これはシンプルで且つ良いと私は思った、
しかし如何せんそこに絵が到達するには今
少しの取り組みが必要じゃないか?と、、
このようなモノが見え隠れしたのが昨年の
個展だったのである。
私は僅かな助言をした。
大きな絵を描いてみない?
ただ単に大きな作品を描くのではなく、今回
の個展で並べた絵を、一枚に凝縮するような
絵を描いてみては?
あらゆる角度で”人の中にある姿”を今は
描いているけど、それを一枚で表すのではな
く”現して”みてくれない?
ある意味、”不気味な一人の人間を”・・・
という宿題を課したのであった。
何となく分かっていた。それまでの絵は
詩作に近かった、しかし私が提示したもの
は”小説”である。
小説は一つの事を伝えるために、場合によ
っては何万語も費やす・・・
竜馬がゆく
司馬遼太郎は竜馬以外を書いた訳ではない
あくまで竜馬である・・・・
結果はある一つの事を伝達することでしかな
い。
しかし、読んだ人間が受けたのは
竜馬の時系列の活躍か?
この作業を一度して欲しかったのである。
決して詩作が悪いわけではない。
瞬発的に出来るモノと、かなりの制御と材料
を必要とする小説では違うような気がする
というのは大きな間違いで、実は逆転して
考えれば、小説を凝縮したのが詩作でもある。
その瞬発力の根幹にはやはり小説的材料の
凝縮が必要となる・・・
この相互の作業を知らずして詩作に励んでも・・
先に大きくなるような感じを受けないのと同時に
小説的なものも知らないまま終わりそうな気がし
たのである・・
そして数ヶ月後、あるコンペに入選した。
その作品は確かにそれまでのモノとは見違える
ようなすばらしい出来だった。

その直後、私は次の宿題を彼女に課した。
小さいモノを一つのテーマで連作で描いてく
れない?
これは単純に先に書いた物の分解作業に近いの
だが、テーマという茫漠としたものに、一点集
中で向かう、そうすることにより、実は一点一
点があまり意味のないものと化す。何が残るか、
テーマがより浮かび上がるか否かという事であ
る。
一枚の絵を描くのに、箱に収納する一枚一枚の
絵という材料、その箱から傷つけず取り出して
いく一枚の絵・・
この答えが、実は現在展覧している
「不器用な色たち」の絵画の部分である。
一枚から取り出した一枚一枚の絵である・・
ここで想いもしない答えをKAPPAちゃんが出して
きた。実はこの「不器用な色たち」はF4で25枚
存在するのだが、これを全て足せば、出品の
基準サイズである100号となるのである。
物理的にKAPPAちゃんは分解していたのである。
この25枚の小品が出来てきた時に新たな宿題を
彼女に課した・・・
正直、これはどうかな?と少し悩んだのだが、、
それは?
立体を作らない?
というモノだった。
これを根拠なく言ったつもりはない。実はここ
までやって来た作業の中で、どうしても付け加
えたかったのだ。それは、、、
描いてきた人間を
取り出してみない?ということであった。
これを、私は見たかった。
これまでキャンバスに描いた様々な不思議な人間?
これを一度具体的に見てみたかった・・
どれほどのものか?
昨年KAPPAちゃんととある美術館へ同世代の知り合
いの女の子の展覧を見に行った。
そこにその女の子は立体を展示していた。
ここでKAPPAちゃんと話したのは
この美術館という環境を羨ましいと感じるか?
恐ろしいと感じるか?
私は正直に伝えたかったのは後者である。
本当の意味で万人に向き合う芸術作品とは
相当な強度を持っていなくては、簡単に
”へしゃげて”しまう。本当に自分にそこ
までの強度があるかないか?この判断が
実は大事な事なのだと思う。
なにも臆病になれというのではない。
しかしその女の子の作品を前に感じたのは
完璧ではないがそれなりの強度を保っていた。。
単純に”出てくる”ものがあった・・・
このときKAPPAちゃんと話し感じて欲しかっ
たのは・・
実存。
360°実存。
そんな絵をいつか描いて欲しいという
私の欲求であった・・・
そんな感覚を養って欲しかった。
だからその研究のために
立体を作って欲しかったのである。
立体に曖昧な着地点はない。ディティールの
粗雑さが全体を崩したり、なにかいい加減な
処理をしてお茶を濁しても、結果は許してく
れず全て崩壊する。
この構造を掴めば多分絵は大きく変わり、もっと
進化するんじゃないか?と考えたのでした。。
それが今回の立体作品です。
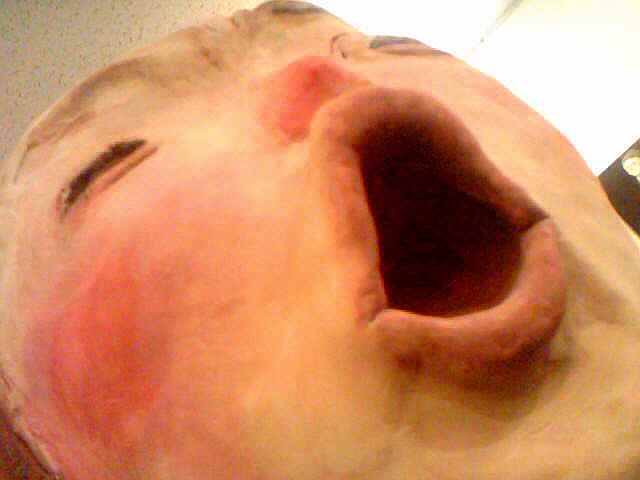
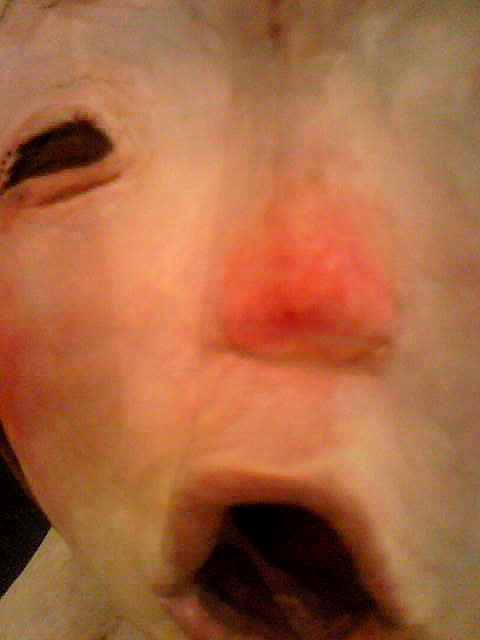
完璧ではけっして無い、強度も十分とは言えない
しかし、可能性がそこかしこと一杯顔を覗かして
いるのは間違いない。。

私は彼女が
今以上に飛躍する確信めいたものを今回掴んだ
ような気がした。
KAPPAちゃんと我々の挑戦はまだ始まったばっかり
だ!!



