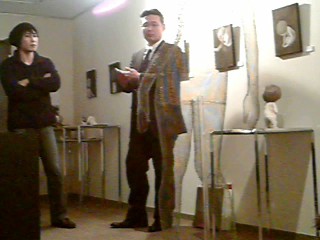京都→尼崎→宇治田原・鷲峰庵→京都→上海→京都
February 27,2010
展覧会と展覧会の間が
実は忙しい・・
一昨日は
3月1日から我々のホームページ
に登場していただく
中井幸子(なかいさちこ)さんと
ホームページブログの最終的な打ち合わせ
と秋の個展の打ち合わせ・・・
昨日は朝から
尼崎に懇意にしているデザイナーさん
に借りていた什器返却と、今進めている
プロダクト計画(COMBINEとは直接的な
関係はないが、、)の生産計画の打ち
合わせ、、、、
、エッと驚くような
量が計画されていて・・・大丈夫か?
と不安になったのもつかの間
携帯電話に
某有名美術館の館長から直々の電話、、
瞬間、、、身体に緊張が走った!
次回のエトリさんの展覧に興味を持って
いただいたようで、様々な質問と、、、
大変嬉しかったのだが
お誉めの言葉までいただいた。
お忙しいので中々スケジュールの調整
が難しいとの事なのだが、なんとか
お越しいただきたい限り・・・です。。
という事で、次に高松で展開していた
田村さんの作品を一部返却するために
京都宇治田原へ車を飛ばす!
京都→尼崎→京都宇治田原
鷲峰庵へ
やはり高速道路のネットワークはすごい
田村さんと高松の結果報告と今後の
計画の打ち合わせ・・
山奥の鷲峰庵では時間が止まる・・
ダルマストーブにまき木を焚いて
田村さんとゆったりと話し込む、、
昨年からの慌ただしい時間を振り返り
今後の方向性を確認しあった。。
何か良いものが出来そうな予感!
フッと時計を見ると次の予定が・・・
慌ててギャラリーに車を飛ばす・・
次は松本くんがギャラリーで待って
いる・・・
その間、山本幸夫さんから電話
5月の展覧会の打ち合わせの件だ・・
作品が少しづつ出来あがってきたので
見に行かなくてはいけない・・
明日(今日)行く事にした。。。。
ドキドキワクワクである・・・・・
というような電話を挟んでギャラリー
に戻ると、松本くんがまっていてくれて
当ホームページでも彼がブログで紹介
してくれているが、新婚旅行で行った
カンボジアのお土産を持って来てくれた
のであった。。。
カンボジアの話や、これから秋までの
スケジュールの確認。
彼は春から団体展3連発、、その間、、
当ギャラリーでの個展と、それ以外にも
私からの依頼である作画・・・・・
非情にもタイトな計画を打ち立てたのだが
頑張ってくれそうで、、、なんとか形に
しなくてはと改めてお互い決意を固めた!!
松本くんが帰ってから
朝からのメールをチェックすると
上海から怒涛のメールラッシュ
有難い事に
KFLのFさんがすべて防御??というのか
処理を進めてくれていた・・・が3月の
Fさんの出張までに詳細な資料の準備が
必要に・・・
中国の人の猛ラッシュ・・・
これは本当にスゴイ・・・・
というか、、LAOさんとぽんちゃんが凄いのか??
メールでFさんに返すのがもどかしかったので
即時お礼の電話。。。
というような一日・・・・だった。。。
来週の月曜日は
エトリさんの個展設営だ
3月は忙しくなりそうである・・・
共生循環
February 24,2010
芸術の表現テーマは基本的に何を軸に
しようとも構わないと思う。
幾千幾万も存在する考え方や、それを
現す手法は同様に存在すると思う。。
しかし、だからと言って我々の仕事を
考えた場合、色々なものを選択し種々
雑多な見え方で果たして良いのだろうか?
という部分に突き当たる・・・
それは違うように思うのである・・
何か偏狭な、且つ具体的なものに限定をする
必要は無いのかもしれないが、ある程度の
範囲というものが無いと、客観的に見た場合
”なにがやりたいのか?”
”なにを言いたいのか?”
という事が著しくぼやけてしまうような気が
するのである。。
この場合、どういった形でそれを集約するのか
は色んな方法が存在すると思うが、大にして絵画
を中心に考えた場合、表層的な雰囲気で収攬する
方法や、マテリアルに限定するような方法が目に
付く・・
基本的には集約する人間の趣味思考が強く働くの
は良くわかるが、この程度の考えでは・・・
と個人的には少し懐疑的な感想をいつも抱いている・・
結局、何を訴えているのか?良くわからない・・
この部分の程度が実は非常に重要なのではないか?
と生意気にも常に考えているのである。。
私はこれまであえて其の辺りの範囲について言明
してこなかったのだが、思うところがありある程度
明白にすべきではないか?と今は考えております・・
それは今後の必要性に駆られた部分に摘まされた
というような事が一番大きな理由なのですが、、
今後の必要性とは何かと言えば、、、やはり異文化圏
との交流に際して、其の辺りの軸が明確でないと行動の
主体性が茫漠として、、先述同様の・・
”なにがやりたいのか?”
”なにを言いたいのか?”
”なんのためにそれをしているのか?”
”なぜそのために、このアートを選択したのか?”
という事柄に著しく抵触するのと同時に、明確さを欠くと
自らの主体性を埋没させてしまう結論にしかならないので
は?という危惧を感じたからです・・
我々の仕事の根幹はモノを直接作り生み出す分けではない
ので、、”選択”という部分が大きなウェートを占めます。
ある意味、其の選択ラインナップにより、考え方を表出し
ているという結論にいたるのかも知れません。
しかしながら、根本的な本質を考えれば
何をもって”選択したのか?”ここの明確さがシンプル
且つ”感じやすい”内容で絶対必要だと私は思うのです。
それが我々の仕事の本義となるように思います。
この時代にCOMBINEをディレクションするにあたり、
私が考えているCOMBINE芸術のコンテクスト及び
コンセプトとは、、、、、
共生と循環
これがテーマです。
実は私がこれまでCOMBINEの作家を選択する際
必ずこのテーマを下敷きにし必ずそれに相応
しているかどうかのコンセプトを判断してきた
のであります。
だから私は各作家とは、作品を見る時間よりも
考え方を聴取する時間に重きを置いてきたのも
この事情があるからです・・
いくら内容的に良くても、この部分について
なんの琴線も弾かれない場は選択はしてきません
でした。。
。。。。。。。。。。。。。。。。
共生とは共棲で非ず、どちらかと言えば法然が説く
”ともいき”・・・という方が感覚的には正確で
それを持って如何に循環させていくか?という事です。
さほど斬新な考えではなく、世間一般にありふれた道徳
概念の延長線上なのかもしれませんが、しかし、その当
たり前であり且つありふれたものが、この世紀を境に著
しく破綻を来たしているのも又事実なのではないかと思
う次第なのです・・
人間を中心とした生き物の生息圏で今起こっている問題の
根源的箇所とは、実はすべてこの共生循環の破綻に通じる
ように私は感じるのです。
これは個人、社会、国家、生き物全般に全て共通の課題
として提示されたものであり、それを如何に乗り越えて
いくかが、この21世紀前半の最大課題であり、哲学も
宗教も科学も、、、今、それを乗り越える論理を様々な
パートで模索しているような気がするのです・・・・・
これは例え一個人が又一国家が乗り越えたとしても、必ず
その主観的発想からの論理では他人や他国への問題の皺
寄せが発生する状況があり、前世紀との大きな違いは、これら
全てが密度高く連関しあっているという事であると想像に難く
ない事実があります。
キリスト教的史観で踏破できてもイスラム教では矛盾にしかな
らない。というような事を含め、全てこれまでの概念から脱却
し、ある程度の妥協と調和、エゴの抑制と幸福のシェアーとい
う人間も動物を含めた生き物の一種であるというシンプルな
共通認識と高い包容力が否応なく求められているような気がす
るのです。
例えば・・
石油というものがあります。
これは発見とこれを活用する文明の利器の開発当初から
必ず枯渇するものであるということは分かっていた筈です。
しかしながらどうであろうか?このエネルギー燃料の安全
な代替エネルギーは今何かの具体的兆しがあるのだろうか?
いずれ無くなるものである。どうなくなるのか?地球から
無くなるのである・・では最後に保有するのはどこなのか?
それ以上に、限られたものをどの様に分配するのか?
国家間で確保できれば本質的な問題は解決できるのか?
当然、国際政治学的な国益を前提とした現実的な話は理解
できる。しかし明らかに行き着く果ての”破綻も”観念的
なロマンティックな妄想であっても具体的理解を生み出せる。
先進国、経済発展著しい国、軍事力、等々、様々な関数が
関与してくる法則において、人間という生き物はこれを
どのように解決していくのか?・・・・・・・・・・
例えば
水というものがある。
水という液体の存在はどこがスタートかは別にして、海の水が蒸
発し、雲、水蒸気を発し液体として地上に降り注ぐ。それが山で
治水され川に流れ又海に還元される。その間人間は、肉体に必要
な液体として水を享受する・・・これが営々と続いてきた人間と
生き物たちの生命維持の循環法則である・・・
しかしどうであろうか?
温暖化により必要以上の雨が降り注ぎ、災厄をもたらし、過度の
開発により生じた自然破壊が、山野を蝕み、、砂漠化という生命
力の破壊まで行き着いた場合、、、果たして水の循環は楽観的に
客観視していて保てるのか否か?
なにかが循環の経路に著しく混濁して、その流れをせき止めている
事は明白である・・しかし何をやめて何を促進するのか?それは
本当に何のエゴもなく妥当性を維持できているのか????
水メジャーなる言葉まで生まれてきていて
フランスなどがその最先端技術と世界展開により、水という人間
共通の資源を寡占しかねない状況だと聞き及ぶ・・・
例え国家の資源として見た目に存在していても、それを飲料や
上下水などという人間生活に欠かせない物へと変換するのに
他国のシステムが作動しないと利用できないとなれば、国家の
資源などというのは如何ほどの価値もなくなる・・・・
所謂、水植民地化論議である・・
本当に有史以前から人間が生命を維持するために営まれてきた
循環の補完要素として機能しているのか???
人口増ということがある。
世界人口は増え続けている一方だ。当然今問題の二酸化炭素の排出
もこのまま行けば比例して増大するのは目に見えている。。
しかしその問題以前に、それだけの人口増に対して食料が追いつか
ないという事が、科学者のデーターとして現在知られている・・
所謂食料危機である。
$や金、資源、それぞれ兌換出来うる価値の源泉として今世界中で
取引されているが、果たして食料という人間が生きていくための糧
が地球規模で枯渇し、ない状態の中で本当にそれらは価値を維持し
ていけるのか?
果たしてその時、食料の分配はどのように行われるのか?
限られた人間の生命を維持することしか出来ない食料事情の中で
生きる者と死ぬ者は誰が線を引くのか?・・・・・・・
これらは実はただの一例にしか過ぎない。
もっと言えば極端な悲観論なのかもしれない。
しかし想像に難くない部分もつかみ取れる。
その根源とはなにか?
私はやはり全ての循環が破綻を来し始めている
というように感じるのである・・・・
いろいろな何世代にも亘る世紀で同じような
厭世観はあったと思う。。しかしそれらの規模は
今と同じではない事は皆理解できていると思う。
当然そこにはもう使い尽くされた感のある言葉
であるが、、グローバル化という今世紀の地球の
問題を定義する前提が生まれているからである。。
これが現代の最大の問題なのではないか?
地球規模で共生循環を考えなくてはならない
時代!
現代というのは
本義として”同時代感覚”であると思う。。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
肉体的に劣る障害をもった人はどの国にでも存在します。
当然その人達は同じ帰属する国家でその助けをしなくては
ならない。それは当然最初から必要とされる経費であり
そんなものは別の派生経費でもなんでもない。と言うことは
社会を維持する為に、ある意味営々と循環させるためには
経済の活動の中に必ずカウントしなければならないコスト
という認識があってしかるべきである・・・
私の小さな時分、年金というものの概念は、若者が老齢の
人に対し社会的コスト支出するために存在すると教わった
筈なのだが、今どうであろう?
いつの間にか自らの掛け金としてしか論議されていない。
当然年代が逆三角形の人口分布になるような人口減の状況
があったとしても、基本的な社会コストが変わるという
事は無いはずであり、なんとしてもその課題は克服しな
ければならない筈なのである・・・・・
当然分かっていた、もしくは奇しくも現れた現象、いずれ
にしても今生きている我々は循環を止める訳にはいかない
筈であり、それを乗り越えなくてはならない・・
我々は、、、
これらと同じような事を世界という規模で拡大して考え
その為に、、、
実はグローニカルな視点を持たなくてはならないのである・・
いろいろな哲学が道徳を生み出し人間という生き物を、人間た
らしめる為に機能してきたが、果たして生命の危機を感じるよ
うな状況が目の前に迫った時、人間本来が持たなければいけな
い愛他精神を本当に具体化できるのか?これほど高度に成熟し
た国家や社会の中で、改めてその人間を含めた生き物の根源的
な尊さの序列を構築できるのか?文化や歴史観、国境を越えて
・・・・・
科学技術の進化は当然待ち望むべき光ではある
しかし、その技術を手に入れたとき、問題はそれを
どう活かすのか?という事に当然なる・・・・
その時、本当に必要なものとは何か?
人間の人間に対する考え方なのではないか?
と思うのと同時に、それはひいては生き物全体に
感じる部分でないといけないのではないか?と
思うのである。。。
私はこれらから
全ての問題発生の根幹が
共生循環の破綻にあると定義しているのであるが
それと
芸術はどう関わるのか?という部分なのだが
私はこれらのことを例え直接的な解決に結びつく
モノで無いにしても、言語、史観、宗教、その他の
諸々を含め、それらを超越でき共通の認識を得られる
唯一の存在こそが芸術なのではないか?と考えるのです・・・
芸術の世界の本質は”人間の生死に立脚したものであり”
どの方向からアプローチしたとしても、必ずそこに
帰結すると私は思うです・・
一点の芸術作品が如何ほどの事を発揮するか?と
疑問があって当然です。
しかし優れた芸術作品は必ず個人に対して浸透できる
力を持っています。そこに力の源泉が必ずあると確信する
のと同時に、その無限の積算の可能性が流動することに
より、世界共通言語としての芸術の必要性が増す筈だと
考えるのです。。。。。。
特に”現代美術”と呼ばれるものの本質的生息域とは
これらと表裏一体であり、共棲していると私は判断している
のです。
このとき私は
COMBINEのこれら問題についての処方を
どの論理で向き合うかと言えば・・
東洋的な物事の考え方という方向性と、そこから熟成された
日本的な捉え方という事を軸として考えているのです。
それは何かと言えば
欧米の二元論的な排他の論理ではなく
受容するという考え方
全てを受け入れて、そこから問題を乗り越え調和を模索し生み出
す触媒としての要素をCOMBINEでは各作家の芸術性の中に見いだし
ているのです。
何が現代の問題として存在しているのか?
その角度と、それについての日本人的な解釈の感度・・・・
これが私にはもっとも大事なことなのです。。。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
声高に”現代美術”などと連呼する輩がいるが
どうも私にはその現代美術の定義が
理解しかねるのである・・・・・・
眉間に傷を持つ男!
February 23,2010
突然病気はやってくる・・
何を唐突に、、と思われるが、、
ある日突然眉間に出来物が、、、
しばらくほっておいたら
ドンドン広がり、、、、
実にみっともない状態に・・・・
しかも顔の半分が痺れだし、、痛みが
出てきた・・・・
う----------ん、、これは自然治癒の限界点
を超えた状態かも。。。。。
ということで急いで医者に行ったところ
”ヘルペス”です・・・と簡単な一言・・
どうすれば?と聴くや否や、、、
一週間点滴を打ってくださいという素っ気無い回答
時間を聞くと、、一時間半・・・・
一週間も毎日一時間半も点滴に避けるかと思い
それをしないと絶対に治りませんか?と聞き返すと
治りますよ、放置していても・・・・
しかし、、、、
しかし???
顔面神経痛の後遺症が残るかも・・・・・
えぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ・・・・・・
大した顔ではないが、、それでも親からもらった顔、、、
男の顔は”履歴書”とも言う・・
仕方ないので通ったが、、、、、
今やっと良くはなって来たが
悲しいかな
眉間に痕が・・・・・・・・・・
青野女史にそのことを言うと
「眉間に傷を持つ男!」
カッコイイじゃん!
って・・・・・・
なんだかなぁ~な今日この頃である。。。。。
壷中天
February 21,2010
今から思うと、いろいろ悩みがあった。
その時々は真剣に悩み、自身の生活の
中でその悩みはかなり大きなウェート
を占めていた。
しかし、時間がたち思い返すと、、、
“なんであんな事くらいで悩んでいたんだろう?”
と思うことが多々ある。
自分が成長した?というよりも経験の差なの
かなとも考える。
もちろんどんな解決の形であったとしても、、、
とりあえずは経過したわけで、、そのようなことが
同じ悩みとして改めて降ってくる事はない。。。。
だからか少し余裕をもって客観的に考える事が出
きるのだろう。
しかし仕事の場合は少し違う。自分が経験した事を
後輩がもしくは部下がというように間接的に経験値を
分かち合わなければならない状況が生まれ、完全に
他人の経験というような距離を取れない状況が介在
する。
本質は一緒なのだが、環境がその時々によって違い、
本筋の解決策は同様なのだが枝葉の部分で躓く事も
ある。当たり前である本質は他人の解決を見る訳で、
新たな経験でもある・・・・
悩みは尽きる事がない、人間は喜怒哀楽という感情
を持ち合わせているがその全てに渡って悩みは存在
する。
悩みの背面に喜びが存在し、悩みと同居する怒り,
怒ってしまう悩み、悩み哀しみ、哀しみ悩み、悩みか
らの解放策としての楽しみ,,悩む楽しみが存在する。
学生時分は基本的にはバーチャルな世界観で議論をする。
いわゆるシミレーションである。同じ悩みに対しても、
ネガティブな捉え方をするもの、ポジティブに向かう
もの、と両極存在するが意外とネガティブそれも厭世的
な考えが出てくることが多かった。
私の学生時分の世相はバブル真っ最中だった。
どこか享楽的なにおいが現実世界に漂い、労せずして
豊満な世界が約束されているような錯覚があった。
そのせいなのか楽観的で無責任な厭世観があったのは
事実です。
あるとき後輩と話をしているとき、テーマとして宇宙
の話がでた。
宇宙という言葉は知っているが、では実態としての
宇宙というと説明がつかない。
大体規模がわからないし、“果て”エンド“終わり”
があるのか無いのかが解らない。
地球にても昔は水平線の向こうは滝になっていると
いう論理が基本であったように、現在一般の我々から
すると宇宙の果てについての観念は水平線の向こうは
滝という論理と同様である。
そんな事を科学としてではなく哲学的論理で考えると
ものすごく深みにはまってしまう。
地球創生からの時間のなかで我々の人生は、時計に
例えると1秒にも満たないという話がよくあるが、
ものすごい虚無感を感じてしまう。
人に言わすとだから人間の存在はちっぽけで、その
人間の悩みなんか鼻くそほどの価値もないという、
相対性のかけらもない比較にて論理を展開する。
しかし私はかえってその話は虚無感と虚脱感を感じてしまう。
私が宇宙の実態の無い大きさに悩み虚脱感を感じていると
後輩は、、、、
「先輩!仮に宇宙の果てが数値として先輩に理解出来たとし
ましょう」
「その宇宙の範囲が実は水槽なんです!」
「?????」
「実はガリバーみたいな大きな人間がその水槽をインテリア
として家に飾ってるんですよ、、。。
そして地球やいろいろの星を栽培というのか飼育というのか、
とにかく鑑賞してるんですよ!なんか壮大でしょ!へっへっ」
「その上にまだ大きなガリバーみたいなやつが。。。。。」
。。。。。。。。。。。。。。
芸術家、、いや全ての仕事の世界観は
壺のように小さな入口のようだが
とんでもなく
奥行きがあり
広大無辺でなくてはならない・・
そんな事への、、憧れが止む事が無い・・・
自分の壷中天を
早く具体的として
持たなければ・・